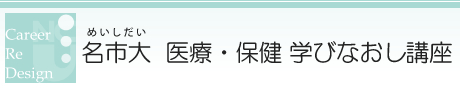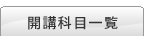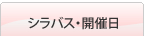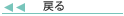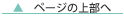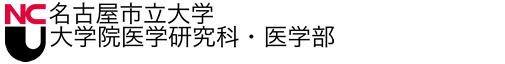シラバス・開講スケジュールのご案内
「名市大 医療・保健 学びなおし講座 シラバス」履歴です。
各講座の詳細なシラバス(講座詳細)については科目名の「 PDFファイル」のリンクをご覧下さい。
PDFファイル」のリンクをご覧下さい。
- 目次
- 2024年度 履歴
- 2023年度 履歴
- 2022年度 履歴
- 2021年度 履歴
- 2020年度 履歴
- 2019年度 履歴
- 2018年度 履歴
- 2017年度 履歴
- 2016年度 履歴
- 2015年度 履歴
- 2014年度 履歴
- 2013年度 履歴
- 2012年度 履歴
- 2011年度 履歴
- 2010年度 履歴
- 2009年度 履歴
- 2008年度 履歴
![]() [最新案内へ戻る]
[最新案内へ戻る]
 名市大 医療・保健 学びなおし講座 シラバス
名市大 医療・保健 学びなおし講座 シラバス
| 学期 | 科目No. | 科目名 | 曜日 | 科目概要および期待される成果 / 目標とする資格 |
|---|---|---|---|---|
| コーディネーター | ||||
| 2024年 春期 |
24-101 |
発達障害臨床に関する様々なトピックス ー全ライフステージにおける診療と支援の視点からー  講座詳細
(PDF:196KB)
講座詳細
(PDF:196KB)
|
火 | 【概要】発達障害という疾患は、最近では非常に身近なものになりました。発達障害は子どもだけでなく、おとなになっても続いたり、おとなになって初めて顕在化したりする例も少なくなく、ライフスパン全体を通して、診療を含めた支援が必要です。発達障害臨床では医療にとどまらず、子育て、教育、就労といった日常生活全般に深く関わる支援が求められます。発達障害児者の診療と支援に関わる方々に、いろいろな視点から学べるよう話題を提供します。 |
|
名古屋市立大学大学院医学研究科 こころの発達医学寄附講座 教授 山田敦朗 教授 永井幸代 |
【期待される成果】発達障害を診療できる医療機関は限られていて、受診まで長い待機期間が発生しています。いろいろな方に発達障害について学んで頂き、現状では限られている診療や支援のすそ野が広がるとよいです。 | |||
| 【目標とする資格】精神科専門医または小児科専門医を持っている医師の方が子どものこころ専門医の資格を取得することを目的とします。また日本児童青年精神医学会の認定医、日本小児精神神経学会の認定医取得にも役立ちます。専門医取得中の医師や、医師以外の保健師、看護師、臨床心理士、公認心理士師、精神保健福祉士、教員、スクールカウンセラー、ケースワーカーなど発達にかかわる様々な方のスキルアップにも役立ちます。 | ||||
| 24-102 |
リハビリテーション医療と関連分野の最前線
講座詳細  (PDF:193KB)
(PDF:193KB)
|
水 | 【概要】リハビリテーション医療の特徴は、疾病によって生じた機能あるいは能力の障害を見極め、これに対してリハビリテーション科医を中心に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護士など多様な専門スタッフが協働して障がい者(児)個々の問題にアプローチする事にある。したがって、疾病自体の治療を目的とする関連分野との密な連携が重要である。本講座では、リハビリテーション医療の主たる関連分野である中枢神経疾患、神経筋疾患、関節リウマチ、骨関節疾患やスポーツ障害などに関する最新の知見についてわかりやすく解説していただく。 | |
| 名古屋市立大学大学院医学研究科 リハビリテーション医学分野 教授 岡本秀貴 |
【期待される成果】中枢・末梢神経疾患や運動器疾患あるいはスポーツ障害などを基盤とした機能・能力障害について理解を深めるとともに、リハビリテーション医療あるいは関連分野における最新の診断・治療について学んでいただく。こうした学習を通じて、医療関係者が国民に対して質の高い医療・福祉サービスを提供し得る。 | |||
| 24-103 |
感染症学びなおし~基本から最新情報まで~
講座詳細  (PDF:192KB)
(PDF:192KB)
|
木 | 【概要】2019年末の出現から4年を経過した現在もなお、わが国の新型コロナウイルス感染症は終息に至っていません。近年新興・再興感染症の波が到来するインターバルが短くなってきており、医療従事者のみならず日本中、世界中の人々が今後の感染症パンデミックへの備える必要があります。病原体の性質、病原性、伝搬性によって対応に相応の振れ幅はあるものの、感染症に対するアプローチの根幹は変わりません。本講座では、日頃より感染症診療,感染管理に関わっているさまざまな職種の専門家とともに、皆さんに是非知っておいて頂きたい感染症の基本から最新情報までを学習する機会にしたいと思います。 | |
| 名古屋市立大学大学院医学研究科 臨床感染制御学分野 教授 中村 敦 |
【期待される成果】感染症に関する基本的知識に加え,最新の情報や現在抱えているさまざまな問題を学ぶことにより,安心・安全で質の高い医療を提供できることを目指します. | |||
| 【目標とする資格】ICD制度協議会:インフェクションコントロールドクター(ICD),日本感染症学会感染症専門医,日本化学療法学会:抗菌化学療法認定医・認定歯科医師・認定薬剤師,日本看護協会:感染管理認定看護師(CNIC),日本病院薬剤師会:感染制御認定薬剤師,日本臨床微生物学会感染制御認定臨床微生物検査技師(ICMT) | ||||
| 2024年 秋期 |
24-201 |
痛みの診療最前線2024〜カラダとココロの両面からのアプローチ〜 講座詳細  (PDF:206KB)
(PDF:206KB)
|
火 | 【概要】毎年、痛み診療に直接関わる、あるいは、興味を持っているスタッフが大勢参加してくれています。本年度の学びなおし講座は、術後急性痛からさまざまな慢性痛、小児・高齢者に特有な痛み、器質的疾患から機能的疾患、心理社会要因への対応など、“痛み“に関わる広い領域のレクチャーを企画いたしました。医師、看護師、薬剤師、心理士、理学療法士と、多診療科・多職種からの講師陣を揃え幅広い領域の中での”痛み“の最新情報や、”痛み“診療現場における生の声をお届けいたします。リピーターの参加者にも楽しんで勉強していただけるよう、毎回新たな講師陣を迎え、皆様のご参加をお待ちしております。 |
|
名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野 教授 杉浦 健之 |
【期待される成果】どの専門領域でも、痛みに関わらない医療分野はありません。医師や看護師の他、薬剤師、理学療法士、臨床心理士、管理栄養士、社会福祉士など多職種の方々に、痛み診療に関わるハイレベルな知識と技術を身につけていただき、“多職種チーム医療”に貢献できる人材育成を目指しています。痛みにお困りの方に寄り添い、適切な治療やアドバイスが出来る仲間をますます増やしていきたいと考えております。 | |||
| 【目標とする資格】いたみマネージャー・いたみコーディネイター(日本痛み財団)など | ||||
| 24-202 |
小児医療のすべて Update 2024 講座詳細  (PDF:248KB) (PDF:248KB) |
水 | 【概要】小児医療とは子どもの症状・病気に対して適切な処置を行いつつ心身の健康をサポートするものです。多岐にわたる幅広い知識と対応する能力が望まれます。日本の出生数は減少する一方、医療が大きく進歩したこともあり、新生児から思春期まで様々な病気や問題を抱える子どもの数は多くなりました。その中には感染症やアレルギーだけでなく、心身症や発達障がい、児童虐待といった発達・心理的支援が必要なものまで広く含まれます。小児医療に対する社会的需要は非常に高く、多くの人が現場チームへ参加することが望まれています。本講座では、小児医療の各分野で現在活躍されている方々を講師に迎え、最新の知見を含めた小児医療の実際を学んでいただきたいと思います。 | |
|
名古屋市立大学大学院医学研究科 新生児・小児医学分野 教授 齋藤 伸治 |
【期待される成果】小児医療の学習範囲は幅広く細分化されますが、本コースを受講することで現在小児医療の現場で実際になされている事項を広く効率的に学ぶことができます。身近でよく見られる症状から、稀にしか遭遇しないが知っておくべき疾患までカバーされています。さらに、発達障害や心身症など、これから知っておきたい分野まで見識を深められます。学習を通じて、小児医療に関心を持つ好機になるだけでなく、実際の小児医療の現場へスムーズに参加して活躍する手助けとなると確信しています。 | |||
| 【目標とする資格】小児領域の資格看護師(小児看護専門看護師、小児プライマリケア認定看護師、新生児集中ケア認定看護師)を目指す方や、NCPR(日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法)インストラクター・修了認定を目標にされる方。もちろん、子どもたちの医療現場に興味を持たれている方であれば、現在の小児医療の実際を知る・振り返るために役立つ内容が網羅されています。 | ||||
| 24-203 |
Birth Tour 2024 講座詳細  (PDF:226KB) (PDF:226KB) |
木 | 【概要】分娩は“十人十色”ですが、共通する願いは一つ。それは“安全で安心なお産”です。令和の時代になり、またさらにコロナ禍において少子化の歯止めが効かない日本でも、ハイリスク分娩は確実に増加しています。ひとつひとつの妊娠や分娩に関わる医療も、常に進化しより濃厚なものになっています。世界に誇る高いレベルの日本の周産期医療を維持してさらに向上させるためは、分娩に携わる医師、助産師、看護師、救急救命士、薬剤師や心理士らがよりハイレベルの知識と技術を身につけ“チーム医療”を構築することが重要です。今回初めてツアーに参加される方や更なる“極み”や“深み”や“高み”を追求したい“常に一歩前に突き進む!前のめりな”リピーターの方々にも必ず満足していただけますよう、今年度も“ここでしか言えない、後世に伝えたい症例”を随所に織り込み、汗をかいていただきながらストーリーを展開させます。日常の周産期現場のライブ感溢れる「Birth Tour 2024」へようこそ。物語を完成させるのは貴方です!今年もスタッフ一同、新企画を準備して皆様のパッションに応えるべく、ご参加をお待ちしております。尚、例年お馴染みの「見切り発車オーライ!」に加えこのご時世です。ツアープラン、オプショナルツアーやバースプランは予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。 開始時間は集合時間ではありません。出発時間は厳守です。しっかりと準備し、そして振り返りながら木曜日ゴールデンタイムの熱い夜のオールスターキャストをお楽しみ下さい! | |
|
名古屋市立大学看護学研究科性生殖看護学・助産学 教授 尾崎 康彦 |
【期待される成果】日本は依然として深刻な産婦人科医師や助産師などの産科プロバイダー不足の状態です。30歳代までの産婦人科医師の約70%が女性医師であり、出産や育児によって休業した医師や助産師の現場復帰をサポートすることが今後の日本の周産期医療を支えるために重要です。最新の周産期医療を学び、自信を持って即戦力としての現場復帰を支援する(背中を押す)ことを目標とします。また助産師や看護師が超音波検査や分娩監視装置を学ぶことで、不足する産科医と協力しサポートし合うことができます。院内助産所(バースセンター)の開設を促進したり、さらに初期研修以降産科を学ぶ機会の少なかった医師や救急救命士が妊婦を診察するケースにおいて役立つ知識や技術を習得することができます。 周産期医療従事者の“サロン”的な場を提供します。是非、お仕事の合間の「夕活」にお役立て下さい。このツアーを切り口に、さらなる周産期教育のコミュニティーが“時空を越えて”形成されています。 “地域のお産を守る!”ためにも、今年も“安全なお産をめぐる冒険”はさらにパワーアップしてロングランを更新します。尚、コースディレクターは今年から看護・助産学の世界に飛び込みました!助産のエッセンスをさらに盛り込んでツアー展開します。乞うご期待! | |||
| 【目標とする資格】将来NCPR(新生児蘇生法:日本周産期・新生児医学会)やBLSO・ALSO Japan、J-CIMELSなどの講習会を受講し資格の取得を目指す方や、振り返りをしたい方に役立つ内容を盛り込んでいます。 |