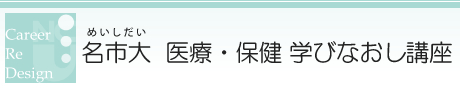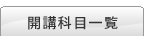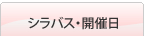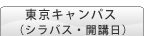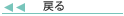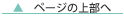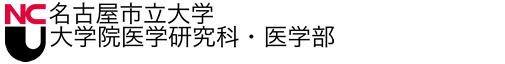名古屋キャンパス(シラバス・開講スケジュールのご案内
名古屋キャンパスの「名市大 医療・保健 学びなおし講座 シラバス(2008年度)」履歴です。
各講座の詳細なシラバス(講座詳細)については科目名の「 PDFファイル」のリンクをご覧下さい。
PDFファイル」のリンクをご覧下さい。
- 目次
- 2024年度 履歴
- 2023年度 履歴
- 2022年度 履歴
- 2021年度 履歴
- 2020年度 履歴
- 2019年度 履歴
- 2018年度 履歴
- 2017年度 履歴
- 2016年度 履歴
- 2015年度 履歴
- 2014年度 履歴
- 2013年度 履歴
- 2012年度 履歴
- 2011年度 履歴
- 2010年度 履歴
- 2009年度 履歴
- 2008年度 履歴
![]() [最新案内へ戻る]
[最新案内へ戻る]
 2008年度 名市大 医療・保健 学びなおし講座 シラバス(名古屋キャンパス)
2008年度 名市大 医療・保健 学びなおし講座 シラバス(名古屋キャンパス)
| 学期 | 科目No. | 科目名 | 曜日 | 科目概要および期待される成果 / 目標とする資格 |
|---|---|---|---|---|
| コーディネーター | ||||
| 3学期 2008年 12月期 |
08-301 |
講座詳細 |
月 | 【概要】フィットネスクラブあるいは自治体の体育施設などで既に運動指導に従事する者に対し、公衆衛生学、運動生理学、スポーツ医学、栄養学などの講義およびストレッチング、有酸素運動、筋力トレーニングなどから構成される実習を行ない、より実戦力のある運動指導者を育成する。 |
| 名古屋市立大学大学院 システム自然科学研究科 生体制御情報系 准教授 髙石 鉄雄 |
【期待される成果】 特定保健指導の対象となった中高齢者に対する運動指導が可能な人材の育成につながる。 | |||
| 08-302 |
講座詳細 |
火 | 【概要】糖尿病、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症、虚血性心疾患、脳梗塞、骨粗鬆症、メタボリックシンドローム、アルコール性肝障害などの生活習慣病の概念、病態、予防と治療の最近の進歩について、食事療法、運動療法や禁煙指導の実際をまじえながら多方面から学習して頂き、医療現場への復帰を促すプログラムです。 | |
| 名古屋市立大学大学院
内分泌・糖尿病内科 准教授 岡山直司 |
【期待される成果】多くの職種の方々が医療現場に復帰された際に、必ず接することのあるであろう生活習慣病を中心に講義内容を厳選しており、その病態、治療、予防などを学習しておくことは将来必ず役立つことと思われます。 | |||
| 08-303 | 認知行動療法入門
講座詳細 ※定員に達しましたため締切りました。 |
水 | 【概要】20世紀を通じてさまざまな精神療法モデルが提唱されてきた。その中で気分障害や不安障害に対して実際に有効であることを実証され、急速に広がっているのが認知行動療法である。認知行動療法は今や、摂食障害、統合失調症、発達障害などにも有望であることが示されている。21世紀の精神科医にとって認知行動療法を応用できることは自らの臨床を磨くために必須である。 | |
| 名古屋市立大学大学院
精神・認知・行動医学 教授 古川壽亮 |
【期待される成果】認知行動療法の基本から講義・実習を始め、いくつかの具体的な疾患ごとのプログラムを実習し、最終的には忙しい日常臨床で認知行動療法を応用できる精神科医をめざす。 | |||
| 08-304 |
講座詳細 |
木 | 【概要】医療技術の進歩により外来クリニックの医療も変貌をとげています。昔の常識が現在では禁忌に近いということもありブラッシュアップはかかせません。育児などで診療の第一線から離れていた医師、看護師、技師のクリニック復帰を支援するコースです。現在第一線で活躍中の方のレベルアップやこの領域に関心のある方も男女を問わず参加いただけます。 | |
| 名古屋市立大学皮膚科 教授 森田明理 名古屋市立大学消化器内科 講師 片岡洋望 |
【期待される成果】外来診療、看護における最新の医療、看護の基礎知識を社会制度的な面も含めて講義することにより、現在第一線の診療業務から離れている医師、看護師、技師のクリニック、病院の外来業務への社会復帰が期待される。 | |||
| 08-305 |
講座詳細 |
金 | 【概要】高齢社会の中、病院における入院患者の6割は65歳以上の高齢者でしめられている。入院している高齢者は入院理由である現疾患以外に、加齢に伴う様々な生理機能の低下により、入院中の治療、療養生活に様々な影響をもたらしている、そこで、今一度、高齢者の身体的・心理的・社会的特徴を再確認し、安全で質の高い高齢者の看護が実施できる能力を習得する。 | |
| 名古屋市立大学看護学部 高齢者看護学 教授 山田紀代美、講師 原沢優子 |
【期待される成果】入院患者の6割以上を占める高齢者について、今回の高齢者の特徴や加齢からくる問題等を再確認することで、現疾患以外の加齢現象や環境との適応などの視点を加えた包括的アセスメント及びそれに基づく援助が可能となる。 |