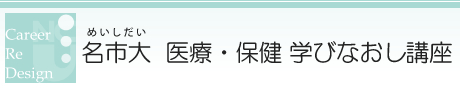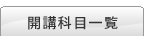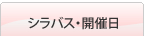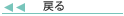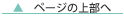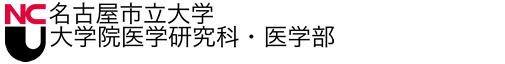シラバス・開講スケジュールのご案内
「名市大 医療・保健 学びなおし講座 シラバス」履歴です。
各講座の詳細なシラバス(講座詳細)については科目名の「 PDFファイル」のリンクをご覧下さい。
PDFファイル」のリンクをご覧下さい。
- 目次
- 2024年度 履歴
- 2023年度 履歴
- 2022年度 履歴
- 2021年度 履歴
- 2020年度 履歴
- 2019年度 履歴
- 2018年度 履歴
- 2017年度 履歴
- 2016年度 履歴
- 2015年度 履歴
- 2014年度 履歴
- 2013年度 履歴
- 2012年度 履歴
- 2011年度 履歴
- 2010年度 履歴
- 2009年度 履歴
- 2008年度 履歴
![]() [最新案内へ戻る]
[最新案内へ戻る]
 名市大 医療・保健 学びなおし講座 シラバス
名市大 医療・保健 学びなおし講座 シラバス
2013年開講のシラバスです。
| 学期 | 科目No. | 科目名 | 曜日 | 科目概要および期待される成果 / 目標とする資格 |
|---|---|---|---|---|
| コーディネーター | ||||
| 2013年 春期 |
13-101 | 必ず役に立つ臨床栄養学 -基礎から応用まで  講座詳細(PDF:187KB) 講座詳細(PDF:187KB) |
火 | 【概要】栄養療法は医療の基本である。近年、急性疾患から慢性疾患、さらには在宅医療、終末期医療においても栄養療法の重要性は再認識されている。臨床に役立つ栄養学を基本から学びなおし、日々の患者管理から栄養サポートチームへの参加まで可能とする知識まで解説する。また、知識のみならず簡単な実習を行うことにより、より栄養管理を身近なものとして考えなおす機会とする。 |
| 名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔・危機管理医学 教授 祖父江和哉 |
【期待される成果】栄養学の基本を身に付け、様々な医療現場における栄養療法をサポートできるようになる。また、実習を通じて栄養療法に関連する手技を学びなおすことにより、実践的な最新技術を習得できる。 | |||
| 13-102 | 脳の健康を考える -認知症、うつ病のいま 講座詳細  (PDF:267KB) (PDF:267KB) |
水 | 【概要】日本の認知症患者は平成14 年の約149 万人から倍増し、現在では推計305 万人に達している。超高齢社会に突入した我が国における認知症患者数の増加は、介護を含めて社会に大きな影響を与えるものと懸念されている。認知症を来す代表的な疾患としてアルツハイマー病があり、その研究は近年、急速に進展しており、症状の軽減、治療法の確立、予防法の発見に期待が高まっている。また、他に認知症を来す疾患にはパーキンソン病およびその類似疾患、脳血管障害などがあり、これらの理解も重要である。さらに、認知症の初期症状にうつ病の様な症状が現れることがある。うつ病が認知症の危険因子であるとする研究もあり、認知症との関連が指摘されている。この講座では、社会的関心の高いこうした認知症ならびにうつ病について、その病態、治療法、介護などについて解説し、介護現場と研究の両面から、認知症とうつ病の解決のためにあるべき方向を考える。 | |
| 名古屋市立大学大学院医学研究科 病態生化学 教授 道川 誠 |
【期待される成果】アルツハイマー病、パーキンソン病、うつ病などの基本病態と治療法について理解するとともに今後の治療法開発の最前線を理解することで、これら疾患に対する正しい対処の仕方を学ぶ。 | |||
| 13-103 | リハビリテーション医療の現状と 関連分野における進歩 講座詳細  (PDF:199KB) (PDF:199KB) |
木 | 【概要】リハビリテーション(リハ)医療の特徴は、疾病によって生じた機能あるいは能力の障害を見極め、これに対してリハ医を中心に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、看護士など多様な専門スタッフが協働して障がい者(児)個々の問題にアプローチする事にある。従って、疾病自体の治療を目的とする治療医学領域との密な連携が重要である。本講座では、リハ医療の主たる関連分野である中枢神経疾患や神経筋疾患、関節リウマチや骨関節疾患あるいはそれに付随するロコモーティブ症候群、スポーツ障害などに対する最新の診断・治療、更には我が国におけるリハサービスの内容と最新の知見についてわかりやすく解説していく。 | |
| 名古屋市立大学病院 リハビリテーション部 部長 和田郁雄 |
【期待される成果】中枢・末梢神経疾患や運動器疾患あるいはスポーツ障害などを基盤とした機能・能力障害について理解を深めるとともに、リハビリテーション医療あるいは関連分野における最新の診断・治療、本邦で提供される福祉サービスの実際について学んでいく。こうした学習を通じて、医療関係者が国民に対して質の高い医療・福祉サービスを提供することを目指す。 | |||
| 2013年 秋期 |
13-201 | 感染症のABCからZまで 講座詳細  (PDF:189KB) (PDF:189KB) |
火 | 【概要】感染症の領域は広くて深い。医学の歴史は感染症に対峙しながら進んできたともいえる。しかし感染症の診断・治療・予防が飛躍的に進歩した今日でもなお、発展途上国のみならず先進国においても未だに解決できない種々の問題が残されている。医療に携わる関係者は最新の情報を含む感染症の知識を身につけ、質の高い医療を提供することが要求されている。 |
| 名古屋市立大学病院 感染制御室 室長 中村 敦 |
【期待される成果】感染症に関する新たな情報、再認識したいさまざまな知識を習得することにより、安心・安全で室の高い医療を提供することを目指す。 | |||
| 13-202 | 発達障害を学ぶ:医学的理解から教育/療育へ 講座詳細  (PDF:238KB) (PDF:238KB) |
水 | 【概要】発達障害に対する理解、指導法の習得、事例研究、などが進み、勉強熱心な関係者が多い。最近では教育現場の教員や療育に携わる関係者の中には、発達障害の医学的知識を知りたい、薬の作用メカニズムを知りたい、脳の仕組みを知りたい、などの声も多くなってきた。本講座では、ADHD を中心に発達障害の医学/生物学的な知識を実験結果からの裏打ちから深め、今後の発達障害児の教育/療育の幅を広げられることを目指す。 | |
| 名古屋市立大学・医学研究科 脳神経生理学 教授 飛田秀樹 名古屋市あけぼの学園 医師 宮地泰士 |
【期待される成果】運動や行動の脳のしくみ、ADHD の診断から病気の医学的理解、環境要因の生物学的影響などについて学び、受講後のさらなる自己勉強がよりスムーズとなるとともに、実際の教育/療育現場での対応法の応用を考える手助けとなる。 | |||
| 13-203 | Birth Tour 2013 - 安全なお産を目指して 講座詳細  (PDF:280KB) (PDF:280KB) |
木 | 【概要】分娩は"十人十色"、しかし願いは一つ"安全なお産"。少子化の進む日本では分娩数は減少しているが、ハイリスク分娩は増加している。またひとつひとつの妊娠や分娩に関わる医療も、より濃厚なものになってきている。日本の妊婦死亡率や新生児死亡率は世界中でも極めて低く、高い周産期医療水準であることを証明している。このレベルを維持するため分娩に携わる医師、助産師、看護師、救命救急士らがより高い知識と技術を身につけることが重要である。 | |
| 名古屋市立大学病院 分娩・成育先端医療センター 副センター長 尾崎康彦 |
【期待される成果】今、日本は依然として深刻な産婦人科医師、助産師不足である。30 歳代までの産婦人科医師の約70%が女性医師であり、出産や育児によって休業した医師や助産師の現場復帰をサポートすることが今後の周産期医療を支えるために重要である。この講座では、最新の周産期医療を学び、自信を持って即戦力としての現場復帰を支援することを目標とする。また、助産師や看護師が超音波検査や分娩監視装置を学ぶことで不足する産科医と協力し、サポートし合うことができる。院内助産所の開設を促進したり、さらに初期研修以降産科を学ぶ機会の少なかった医師や救急救命士が、妊婦を診察するケースにおいて役立つ知識や技術を習得することを目指す。"誕生する新しい命"を前に、貴方は何が出来ますか? |