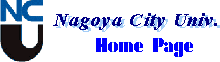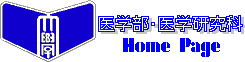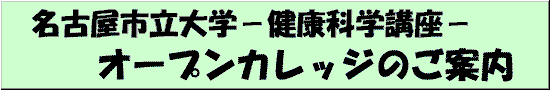
平成19年度 第3期
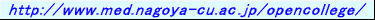
今日、科学技術は大きく進歩し、私たちはその恩恵に浴しています。科学の進歩は日進月歩であり、かつて学んだ知識は古く役立たないものがあります。また、身の回りには多くの情報が氾濫して、どれをどう自分の生活に生かしていくべきか、戸惑うことが多々あります。
本オープンカレッジでは、本学の基礎・臨床分野が蓄積している最新の研究情報を、市民の皆様にわかりやすく解説いたします。皆様には、自己研鑽と再学習の場としてとらえ、日々の生活を実りあるものに、また、将来の生活設計のために役立てていただければ幸いです。
| 開講科目と期間 | No.5 アンチエイジング−美しく老いる 11/21〜1/23 |
| No.6 健康寿命を延ばす−寝たきりにならないために 11/30〜2/1 | |
| 時間は18:30〜20:00の90分授業で週1回、全8回で構成。 受講者は原則として8回を通して受講をお願いします。 |
| 募集定員: | 各科目とも80人 (科目単位で募集し、複数科目受講も可) |
| 受講料: | 各科目とも8,000円 開講初日にお支払いいただきます。 |
| 応募対象: | 教育・保育・福祉関係者、医療関係者、行政自治体関係者、企業 関係者等幅広い社会人及び一般市民(学生・大学院生の聴講可) |
| 応募受付期間: | 平成19年10月22日〜11月13日 |
| 応募方式: | 往復はがき または,E-メール |
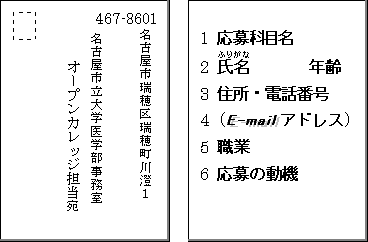
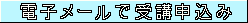

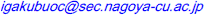
[ 上記はがきと同様に応募申込み事項−6項目−をご記入ください ]
| 選考方法: | 応募人数が定員を大幅に超えた場合は、応募動機も参考にしながら抽選することがあります。 |
| 選考結果: | 平成19年11月16日までにお知らせします。 |
| 問い合わせ先: | 名古屋市立大学医学部事務室 オープンカレッジ担当 〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1 TEL:(052)853-8077 |
2007年 第3期講座概要
科目No.5 アンチエイジング−美しく老いる コーディネーター 小椋祐一郎教授・岡嶋研二教授
すべての生物および細胞には加齢と寿命があります。しかし、最近の医学の進歩により加齢のメカニズムの解明が進み、アンチエイジング(抗加齢)医学という領域の研究が盛んに行われています。永遠の寿命を得ることは不可能ですが、加齢変化を遅らせて、できる限り若々しい肉体を維持しようとするものです。 今回のオープンカレッジでは、基礎医学と臨床医学のさまざまな分野から一線で活躍されている研究者に「アンチエイジング」をテーマにお話をいただくことになっています。多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。
11月21日(水) ホルモン年齢と更年期障害
医学研究科 産科婦人科学 助教 金子さおり
更年期に入ると女性は急激な女性ホルモンの減少により様々な精神的、身体的諸症状に悩まされる方が少なくありません。代表的な症状としては、のぼせ、発汗、倦怠感、うつ状態、不眠、肩こりなどが挙げられますが、その症状は社会的ストレスにより増悪することもあれば、それらの症状が家庭や職場などに影響を及ぼすこともしばしばです。今回は女性が上手に更年期を乗り切り、いつまでも輝き続けられるよう、お手伝いをするつもりでわかりやすくお話をしたいと思います。11月28日(水) 加齢黄斑変性
医学研究科 視覚科学 准教授 安川 力
欧米における成人失明の主要原因である加齢黄斑変性は、日本においても増加傾向にある眼の加齢に関連した疾患です。網膜の中心部である黄斑の下に異常血管が発生し、見ようとする視野の中心が見えなくなったり歪んだりして、多くの場合、1〜2年で視力は著しく障害されます。2003年に光線力学的療法(PDT)が国内でも認可され一定の治療効果が得られるようになりました。また血管新生を抑制する薬剤の臨床試験が多数進行中で、先に認可された欧米でPDTを上回る効果が報告されています。一方、依然として視力障害に陥る症例も少なくなく、日常の生活習慣の改善が予防につながる可能性があり重要です。12月5日(水) 老化に伴う皮膚潰瘍および皮膚がんの予防
医学研究科 加齢・環境皮膚科学 准教授 山口裕史
老年期の皮膚潰瘍(外傷、糖尿病性足潰瘍、膠原病に伴う潰瘍)は様々な原因で生じ、治り難いことが多い。表皮真皮相互作用を通じた部位特異的皮膚の再生医療に対する研究(皮膚の最外層は皮膚の下層からの影響を受け、その場所ごとに相応しい皮膚へと再生すること)を紹介し、治療法を探る。オゾン層破壊が取り沙汰される近年は本邦でも皮膚がん自体が増加傾向にあるが、老年期には光老化に関連し、露光部に生じる皮膚がんの発生頻度も高くなる。紫外線が原因とされる皮膚がんの発生機序を探る。
12月12日(水) 認知症にならないために
医学研究科 神経内科学 病院講師 松川則之
記憶のメカニズムとその破錠による各種認知症の予防・治療法は、世界的に注目度の高い領域である。特に未だ不明な点の多いアルツハイマー型認知症の患者数の急激な増加は先進国において社会的問題になっている。現在までに、脳血管障害に伴う脳血管性認知症の原因・予防法は明らかにされつつあるが、アルツハイマー型認知症については、その病因解明が不十分なために未だ根本的治療法・予防法は不明な点が多い。今回の講義では、これまでに蓄積されたデータから、脳血管性認知症・アルツハイマー型認知症を中心に、どこまで認知症は生活の中で予防できるのかを考えてみたい。12月19日(水) きこえとバランスを保つために−耳鼻咽喉科最新治療の紹介
医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 講師 渡邉暢浩
感覚器一つ一つは小さなものであるが、日常生活のQOLに深く関わっており、これら五官のうち視覚を除く感覚器を耳鼻咽喉科で担当している。感覚器は加齢とともに徐々に機能が低下してくるものが多く、例えば聴覚が低下すれば難聴を来たし、平衡覚(三半規管など)が悪くなれば、ふらつき、めまいを引き起こす。難聴に対する補聴器もいまではアナログからデジタルへ進化しており、更に高度難聴者には人工内耳という人工感覚器の選択肢も出てきた。またふらつきに対する治療としてまだ臨床応用はされていないものもあるが、新しい試みがなされているためこれらを概説する予定である。1月9日(水) 脳のアンチエイジング
医学研究科 医学研究科 脳神経生理学 准教授 飛田秀樹
脳の働きは、複雑な神経回路の組み合わせから成り立っています。一つの神経の働き、神経間の連絡(シナプス伝達)がそのベースとなり働いています。年令とともに脳の働きが低下していることは誰もが実感することです。では脳の機能低下を防止することが出来るのでしょうか?近年、動物を豊かな環境(広い空間での運動量の増加、複数飼育での社会性の増加、探索行動)で飼育することにより、シナプス伝達が亢進し、障害後の運動機能の回復が促進すること、等が分かってきました。脳の機能低下を防止するヒントが隠されている実験結果と思われます。
1月16日(水) 知覚神経刺激作用を介した新しいアンチエイジングの試み
医学研究科 医学研究科 展開医科学 准教授 原田直明
ヒトの成長にはインスリン様成長因子−I(IGF-I)が不可欠だが、その血中濃度は成長が終わる12-14歳頃をピークに低下していく。そのため、IGF-Iを増やすことがアンチエイジングにつながると考えられており、実際IGF-Iには、血圧降下、美肌、および育毛作用もあることが知られている。我々は唐辛子の辛み成分であるカプサイシンと大豆イソフラボンで知覚神経を刺激すると、血液中や皮膚を含む全身の臓器でIGF-Iの生成が増加することを確認した。本講義では、このような知覚神経を刺激する食品成分の、高血圧や肌のしわ、たるみの改善作用および育毛効果について解説する。1月23日(水) 骨,筋肉の老化防止-スポーツによるアンチエイジング-
医学研究科 整形外科学 病院講師 後藤英之
現在、高齢化社会を迎える日本では、国民の健康寿命を延ばし、活力ある持続可能な社会を築くことが推進されています。しかし、筋骨格系の障害(骨、筋肉の老化)は運動能力の低下による健康増進や疾病予防の妨げとなり、健康寿命の延長に大きな影響を与えます。本講義では、運動能力、体力を維持し、骨、筋肉の老化を防止することによって、いつまでも健やかな生活を送るための手段としてスポーツに焦点をあて、老化防止にはどのような運動や強度が適しているのか。運動をするにあたっての留意点などについて述べたいと思います。
科目 No.6 健康寿命を延ばす−寝たきりにならないために− コーディネーター 大塚隆信教授
高齢化社会を迎える日本では、21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)政策のもと、国民の健康寿命を延長して、活力ある持続可能な社会を築くことが国家プロジェクトとして推進されています。この実現のために、健康増進、健康保護、疾病予防があげられています。一方で,脳・心血管・筋骨格系の障害は社会生活の低下や、運動能力の低下を招き、健康増進や疾病予防の妨げとなり、健康寿命の延長に大きな影響を与えます(下記図参照)。そこで、健康寿命を延ばし、より健やかな生活を送るにはどうしたら良いのか、健康的な生活の維持・増進に対して、「寝たきり」にならないためにとの観点から、各専門家による講義を行います。皆様の多数のご参加をお待ちしております
11月30日(金) 脚の動脈硬化−脚の管理で命を守る−
医学研究科 心臓血管外科学 教授 三島 晃
ある一定の距離を歩いた時に脚の筋肉に生じる痛みを、間欠跛行と呼びます。歩行を止めると痛みが消える特徴的な症状ですが、脚の動脈硬化による血流不足などが原因となります。脚の動脈疾患による間欠跛行の患者さんは、15年後の生存率が約20%に過ぎません。同年代の生存率約70%と比べ著しく短命ですが、死因の大半は心臓と脳の血管病です。間欠跛行は全身の血管病変の発症や進行に警鐘を鳴らす大切な兆候と言え、患者さんには心臓や脳を含めた全身の管理が不可欠と理解できます。脚の健康管理を通じて、生活習慣による動脈硬化から命を守る工夫について考えます。12月7日(金) 骨粗鬆症−骨折の予防のために−
医学研究科 整形外科学 病院講師 松下 廉
骨粗鬆症は、骨の量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。日本では、約1,000万人の患者さんがいるといわれておりますが、近年平均寿命が延び、高齢者人口の増加に伴って骨粗鬆症になる患者さんの数は増える傾向にあります。骨粗鬆症は骨折をきたし痛くなるだけではなく、脊椎(背骨)や大腿骨頚部(足の付け根)が骨折すると、歩行困難になる場合もあります。寝たきりになると寿命にも関係してくる重大な疾患のひとつです。骨粗鬆症は、老化現象で避けられない運命ではありません。現在では骨粗鬆症に対して有用なお薬が多数あり、ちゃんと治療すれば直る病気です。今回は、骨粗鬆症の病態、日常生活、食生活において気をつけること、診断方法、また治療法についてわかりやすくお話したいと思います。12月14日(金) 腰部脊柱管狭窄症−高齢者の腰痛、下肢痛の原因
医学研究科 整形外科学 講師 福岡宗良
腰部脊柱管狭窄症とは、脊柱(背骨)の加齢による変化(老化)によって、馬尾神経や神経根が圧迫され、下肢の痛みやしびれ感、歩行障害を生じる病気です。高齢化社会の到来とともに、患者さんは年々増加傾向にあります。今回は、はじめに腰椎(腰骨)の解剖学的な構造(骨や椎間板、靭帯の位置とそのつながり具合)と、脊柱管が狭窄される原因について述べ、次いで脊柱管狭窄症の症状と、自然経過についてお話します。さらに、診断に必要な検査、薬やコルセットなどの保存治療から手術についてもお話する予定です。
12月21日(金) 高齢者の運動療法 −運動器の生活習慣病予防に向けて−
愛知医学大学 運動療育センター 参与 丹羽滋郎
わたくし達が経験する肩こり・肩関節周囲炎(50肩)、腰痛症、膝痛などは、運動器
の生活習慣病と考えます。日常の生活の中で自分の身体を思いどおりに動かしていますが、わたくしたちは、地上で暮らしていますので、常に体重の数倍の負荷を身体に受けています。長い間の生活習慣(毎日の何げない行動)によって、気づくことなく知らず知らずの内に、仕事、作業姿勢、更に加齢による変化が加わって、運動器(上肢、下肢、脊柱)の異常が起こっています。このように考えると、日頃から、種々な動作に際して、筋を意識して身体を動かすことが筋の萎縮を防ぎ、筋の柔軟性を高めます。一日のわずかな時間、普段使わない筋を意識して動かすことを継続することにより、筋力の向上が可能です。またストレッチングより関節の動きも良くなります。長寿のための運動による健康づくりについて述べます。
1月11日(金) 加齢に伴う廃用の病態とその予防に対する運動上の留意点
医学研究科 共同研究教育センター 准教授 和田郁雄
平成12年に導入された介護保険制度の問題点の一つは要支援・要介護1例の多くが更なる機能低下を来している点です。その要因として、いわゆる「廃用(症候群)」が挙げられております。廃用とは「寝たきり」に直結する大変やっかいな状態です。その要因として、骨折、転倒や関節疾患が重要とされ、厚労省は最近、「介護予防の推進に向けた運動器疾患対策に関する検討会」を立ち上げました。講義では骨・関節、筋など運動器系および心肺系の加齢変化が廃用を引き起こすメカニズムについて解説するともに、廃用予防を目的とした運動の効用と注意事項についてお話し致します。1月18日(金) 脳卒中・認知症の予防 -寝たきりにならないために-
医学研究科 神経内科学 准教授 山脇健盛
日本人の平均寿命は著しく伸びており、男性で78歳、女性は85歳に達し、わが国は本格的な高齢社会に突入したといえます。脳卒中と認知症は、いずれも加齢とともに増加する疾患であり、今後ますます増加することが予想されます。また、脳卒中は寝たきりとなる最も多い原因で、脳卒中と認知症を合わせると、寝たきりの方の約半数がこれらの疾患によるものであり、大きな社会問題にもなっています。認知症、脳卒中はある程度予防可能です。これらの診断、治療、そして予防についてわかりやすく解説します。1月25日(金) 関節リウマチ−関節機能温存のために−
医学研究科 整形外科学 病院講師 永谷祐子
関節リウマチは、関節滑膜を病変の主座とする原因不明の炎症性疾患である。炎症を起こした滑膜から炎症性メディエーターが産生され、関節破壊が引き起こされる。これにより日常生活動作が阻害され、生活の質(Quality of life; QOL)が低下することとなる。有病率は人口の約0.3-1.5%とされ、本邦には50万から80万人の患者がいるといわれている。本講義では、関節リウマチの概念、病態についてわかりやすく説明し、さらにQOLを低下させないための最新の治療法についても整形外科、リウマチ専門医の立場から解説する。2月1日(金) 変形性膝関節症−いつまでも元気に歩くために−
医学研究科 整形外科学 准教授 小林正明
今年の敬老の日に、65歳以上の高齢者の総人口に占める割合は21.5%、80歳以上も700万人を突破したと報じられ、すでに高齢化社会は始まっています。車のタイヤがすり減るように関節の軟骨も年齢とともにすり減ってきます。体重を支える下肢の関節、特に膝関節で軟骨がすり減る病気、『変形性膝関節症』になると、膝関節の痛み、腫れ、変形を生じ、日常生活に障害を来したり、進行すると手術が必要になることもあります。変形性膝関節症とは、どのような病気か、どのように予防したり、治療するか、どんな手術があるかなどについて解説します。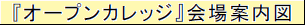
| ※ お車でのご来場はご遠慮下さい。 |
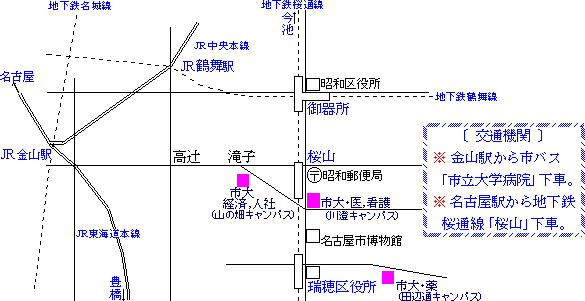 |


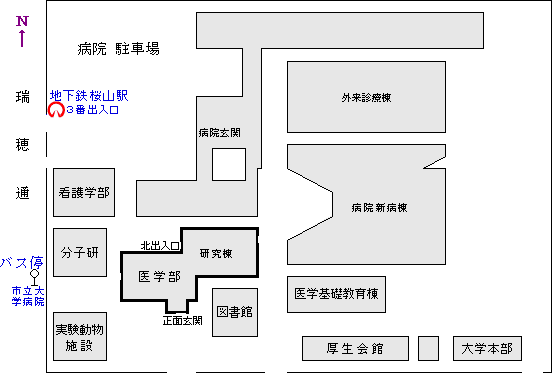
【 医学研究科研究棟11階 講義室A 】
北出入口(病院側から来られるとき)または正面玄関から入って
1階ロビーよりエレベータで11階へおあがりください。

 お茶の水女子大学 公開講座−化学・生物総合管理の再教育講座−
お茶の水女子大学 公開講座−化学・生物総合管理の再教育講座−