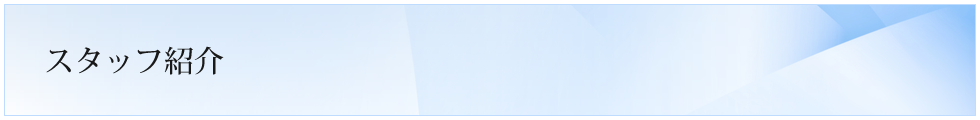名古屋市立大学大学院医学研究科 脳神経生理学のスタッフです。
- 一覧
- 教授
- 准教授
- 助教
- 大学院生
- 研究員
スタッフ一覧
| 役職/所属/学年 | 氏名 | 専門・研究分野 |
|---|---|---|
| 教授 | 飛田 秀樹 | 幹細胞を用いた障害機能の再建、 脳内ドーパミン神経系の生理機能 |
| 准教授 | 田尻 直輝 |
脳内出血モデル動物におけるリハビリテーション意欲が運動機能の改善および脳内変化に与える影響の解析 脳内出血モデル動物に対する人参養栄湯と麻痺側集中使用によるリハビリテーションとの併用効果の検討 新生仔低酸素虚血性白質障害モデル動物に対する細胞移植とリハビリテーションによる機能再建の解析 |
| 助教 | 進藤 麻理子 | |
| ムスティカ デウィ | Vagus Nerve Stimulation by Umami Ingestion Reduces Aggression and Alters Central Amygdala Activity in ADHD Model Rats | |
| 技官 | 櫻井 輝美 |
過去のスタッフ一覧
| 役職/所属/学年 | 氏名 | 専門・研究分野 |
|---|---|---|
| 講師 | 清水 健史 | ミエリン(髄鞘)形成の制御機構 オリゴデンドロサイト異常による精神・神経疾患 |
| 講師 | 石田 章真 | 麻痺側の集中リハビリテーションによる機能回復メカニズムの検討 リハビリによる機能回復と中枢神経系(主に皮質-脳幹-脊髄路)の可塑的変化 |
助教 | 上野 新也 |
教授
飛田 秀樹 HIDA Hideki., Professor
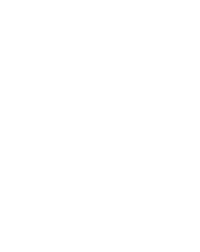
- 主な研究テーマ
-
障害運動機能の再生/再建、リハビリテーション、発育期の情動形成メカニズムの解明
- 幹細胞(ES, iPS細胞)を用いた障害運動機能の再建
- 周産期低酸素虚血性白質障害に対するオリゴデンドロサイト前駆細胞移植
- 病態脳に発現する栄養因子関連物質の解析:生理作用メカニズムの解明
- リハビリテーションによる障害運動機能の再生
- 脳内出血後のリハビリテーション:効果メカニズムの解明
- 周産期低酸素虚血性白質障害に対する発育期リハビリテーション
- リハビリテーションにおける“やる気”の重要性;脳内ドパミン神経系との関連
- 発育期の情動形成メカニズムの解明
- 発達期の環境刺激と情動形成:豊かな環境、うま味刺激
- 発育期うま味摂取による攻撃性変化の解析:腸脳連関(神経性)の脳内機構
- 幹細胞(ES, iPS細胞)を用いた障害運動機能の再建
- 所属学会
-
- 日本生理学会(1991入会、1999評議員)
- 日本神経科学学会(1991入会)
- Society for Neuroscience (北米神経科学会)(1996入会)
- 日本情動研究会(2006年入会)
- 日本周産期・新生児学会
- 日本児童青年精神医学会
- 業績について
- 「研究業績」をご覧ください。
- 大学院進学をお考えの方へメッセージ
-
Q.1 研究室の雰囲気・良いところを教えて下さい。
ファミリー感覚を持った教室を目指しています。
(ドライな人間関係は、日本人の良い部分を無くしていると考えています)Q.2 指導に対する思いを教えて下さい。
『将来、研究者を目指す人』のための指導をしています。Q.3 研究に対する将来的な目標を教えて下さい。
どんな難病の研究でも、研究者自身がその挑戦を諦めてはいけない。なぜなら、患者さんやその家族は挑戦したくてもできないのだから。私は挑戦していく。
准教授
田尻 直輝 TAJIRI Naoki., Associate Professor
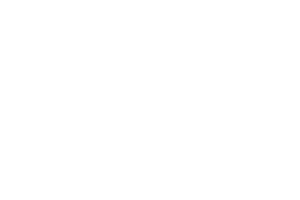
- 主な研究テーマ
-
成熟哺乳類の中枢神経系に一度損傷が起きると、再生・修復が不可能であると考えられてきました。しかし、成体であっても脳室下帯や海馬の歯状回においては神経幹細胞が存在していることが報告されて以来、神経新生の観点から脳梗塞、頭部外傷、パーキンソン病や脊髄損傷などの中枢神経疾患に対する再生医療のアプローチが次々に試みられ、目まぐるしく発展してきました。細胞移植治療効果の代表とされるメカニズムとしては、移植細胞から分泌される神経栄養因子や内因性の神経幹細胞の活性化などによる神経保護・修復効果が挙げられます。また、免疫応答の変化や新生血管の促進などによって、わずかながらも組織再建が考えられ、それが機能回復をもたらしたと示唆されています。しかし、依然として一部のメカニズムしか明らかになっていません。
また、中枢神経疾患の患者に対して、優れたリハビリをすることにより患者の状態が身体面はもちろん、精神面でも著しく好転することが実臨床でも経験され、リハビリは重要な治療の一つであることは明らかではありますが、その作用機序は未だに解明されていません。近い将来、再生医療の発展により、中枢神経が組織学的に修復できたとしても、運動機能・精神機能面の回復が伴っていなければ意味がありません。そこで重要な役割を果たしていくのが、神経機能の再教育とも言われているリハビリです。私は、脳梗塞、頭部外傷、パーキンソン病などの中枢神経疾患を対象とした幹細胞移植療法やリハビリ療法などの有効性や作用機序の検討を行っています。
【対象疾患】脳出血、脳梗塞、頭部外傷、パーキンソン病、脳室周囲白質軟化症など。 - 所属学会
-
- 北米神経科学会(Society for Neuroscience)
- 米国神経修復学会(American Society for Neural Therapy and Repair)
- 日本神経科学学会
- 日本神経化学会
- 日本生理学会(評議員)
- 日本ニューロリハビリテーション学会(理事)
- 日本基礎理学療法学会(評議員/学会企画委員会委員)
- 業績について
- 「研究業績」をご覧ください。
- 大学院進学をお考えの方へメッセージ
- 当研究室では、主に脳障害の病態解明とそれによって失われた機能を再生・再建することを目指した研究に取り組んでいます。基礎から臨床応用に向けて、世界に情報を発信し、社会貢献していくことが我々研究者の喜びです。脳の再生・再建研究に興味がある方は、是非一緒に楽しんで研究して参りましょう!
助教
進藤 麻理子 SHINDO Mariko., Assistant Professor
- 所属学会
-
- 北米神経科学会(Society for Neuroscience)
- 日本神経科学学会
- 日本神経化学会
- 一言コメント
-
末梢免疫系や外部環境からの刺激が中枢神経系にどのような影響を及ぼすのか、脳と身体の連関に関心を持って研究しています。まだまだ学ぶことばかりですが、一つひとつ丁寧に取り組んでいきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
ムスティカ デウィ Dewi Mustika., Assistant Professor

- Main Research Themes
- Vagus Nerve Stimulation by Umami Ingestion Reduces Aggression and Alters Central Amygdala Activity in ADHD Model Rats
- Affiliated Academic Societies
-
- Indonesia Medical Association
- Indonesia Society of Physiology
- The Physiology Society of Japan
- Japan Neuroscience Society
- 一言コメント
-
As an international student from Indonesia who does not speak Japanese, I have received tremendous support not only in conducting research but also in managing daily life in Japan. The laboratory provides a friendly and inclusive environment where open discussion is encouraged, making it easy to share ideas and learn from one another. The teachers are incredibly kind and always ready to offer advice, helping me grow my research and master new techniques. As a mother without local support for childcare, I was touched by how warmly everyone welcomed my daughter and allowed her to stay in the student room while I conducted my experiments. This lab fosters both professional and personal growth in a supportive community.
大学院生
鈴木 美菜(博士課程2年・小児科医) SUZUKI Mina

- 主な研究テーマ
- 学生時代にも当研究室で、新生仔低酸素虚血性白質障害(NWMI)と髄鞘形成に関連した研究を行っていました。医学部卒業後は、2年間の初期臨床研修を経て、その後4年間小児科医として勤務してきました。臨床の現場で新生児医療に携わる中で、NWMIのハイリスク群である早産児・低出生体重児に実施できる本質的な神経保護療法が未だ確立されていない現状に改めて課題を感じ、病態の本質を解明し、治療法の開発に貢献したいという思いから、当研究室に戻って博士課程へ進学しました。NWMIの予後を悪化させる要因のひとつに、出生前の子宮内感染症が挙げられています。現在は、NWMIの病態悪化に対する炎症の寄与、特にオリゴデンドロサイトの分化や運動機能の発達に与える影響についての研究を進めています。将来的には、これらの知見が、より本質的で安全性の高い神経保護療法の開発につなげられること、多様な背景を持つ患者さんたちの支援に役立てることを目指しています。
- 所属学会
-
- 日本生理学会
- 日本小児科学会
- 一言コメント
-
趣味は美術館めぐりです。さまざまな分野で「名古屋飛ばし」が話題となることもありますが、タイミングさえ合えば、名古屋でも質の高い作品に出会える特別展が開催されることも多く、休日にはよく出かけて楽しんでいます。学生証で割引が効くのも嬉しいポイントです。
オラン トヤ(博士課程2年) WULAN Tuya

- 主な研究テーマ
-
オートファジーにおけるATBF1 の機能解析
アルツハイマー病(AD)では、脳にアミロイドβ(Aβ)が蓄積することで神経細胞死が引き起こされます。AD脳では、オートファジーの機能が低下しており、それによりAβの分解が阻害され、Aβの蓄積がさらに亢進すると考えられています。我々は、転写因子ATBF1がAD脳やADモデルマウスの脳神経細胞で顕著に発現が増加し、神経細胞死を促進することを明らかにしました。ATBF1欠損マウス由来のMEF細胞では、オートファジーが促進されることも見出しました。この結果から、AD脳で過剰に発現しているATBF1がオートファジーを抑制している可能性があります。しかし、オートファジーにおけるATBF1の機能は不明であるため、日々研究に取り組んでいます。 - 一言コメント
-
ご指導くださる先生方の丁寧な助言のもと、生化学や生理学の技術を基礎から学び、温かい研究室の皆様に支えられ、日々充実した研究活動に取り込んでいます。
富永 栞(修士課程2年) TOMINAGA Shiori

- 主な研究テーマ
-
- 新生児低酸素虚血性白質障害ラットモデルにおける小脳の研究
- 遺伝子改変マウスのin vivo microdialysis HPLCの実験
- 脳卒中モデルのリハビリによる運動実行系の回路変移と深層学習を用いた解析研究
- 一言コメント
-
Q.1 研究室の雰囲気・良いところを教えて下さい。
活気があり、オープンな雰囲気の研究室です。国内外から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーと日々ディスカッションを交わすことで、専門分野を超えた学びや刺激があります。研究の合間には、おいしいお菓子やごはんを楽しんだり、季節のイベントとしてお花見をしたりと、心が和む時間も大切にされています。Q.2 大学院に進学をお考えの方にアドバイスをお願いします。
学部生のうちから研究室に関わり、技術習得や論文読解に取り組むことで、大学院進学後もスムーズに研究を進められると思います。また、国際的な交流の機会も多いため、語学や異文化理解への意識を持つこともおすすめです。研究室は真剣ながらも温かく、主体的に動けば必ず力になってくれる環境です。Q.3 研究に対する将来的な目標を教えて下さい。
高校時代のSSH活動を通じて脳神経生理学に出会い、研究の世界に引き込まれました。本学の総合生命理学部を卒業後、現在は修士課程で研究を進めています。将来的には博士課程に進学し、自分らしいスタイルで医学研究に新しい風を吹き込める研究者になることを目指しています。