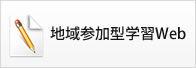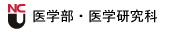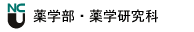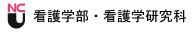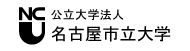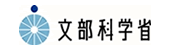評価レポート
大学教育・学生支援推進事業【テーマA】
大学教育推進プログラム
「医療系学部連携チームによる地域参加型学習」
2009年度評価委員会
平成21年度評価報告書
1. 事業の目標達成のための活動状況
本事業はその活動目的として次の5点を掲げている。
- 地域と大学、地域の医療機関と大学の連携による医療人の育成
- 地域や現場の方々とのふれあい、人間的な関わりによる人格形成
- 社会に通用するコミュニケーション能力の習得
- 地域医療に対する連帯感、責任感の自覚
- 医・薬・看のチーム学習によるチーム医療の基盤形成
平成21年度は、年度途中に推進事業として採択されたことから、活動期間は10月からの半年間、対象学生は平成21年度の医・薬・看護学部1年生で任意参加の非正規カリキュラムとして実施された。主な活動して以下のことが行われた。
1)地域と大学、地域の医療機関と大学との連携活動
- 「医療系学部連携チームによる地域参加型学習」説明会が、2009年11月5日にキャッスルプラザにて開催され、12の協力病院から28名、学内より理事長始め17名の教員が参加し、本事業の説明と、協力の要請が行われた。
- 「医療系学部連携チームによる地域参加型学習」キックオフシンポジウムが、2009年12月12日に名古屋市立大学本部棟ホールで開催され、21の地域と医療機関から33名、医・薬・看護学部1年始60名、教員11名、事務職員4名が参加した。記念講演として、神戸大学医学部付属病院薬剤部長、平井みどり氏による「医療人育成における多職種協同教育の意義:神戸大学におけるIPWの取り組み」についての講演と、地域の協力員と学生が地域ごとの小グループに別れ、ワークショップ形式によるH21年度の活動計画の立案が行われた。
2)地域や現場における学生の活動
- 活動地域・施設
- 名古屋市内 9か所
- 山間地・離島 5か所
- 地域の一般病院と診療圏 10か所
- グループの現地調査活動回数 延べ43回、1グループ平均1.8回 (1~4回)
- 現地調査活動参加学生数 延べ161名、1グループ平均6.7名
3)教員による学習支援活動
- 本事業の推進体制として、2009年9月16日に、医・薬・看護学部教授6名、講師1名、助教1名による医療系学部連携教育委員会 Allied Medical Education Committee (AMEC)が設置され、以降毎週水曜日午前の定例委員会が、計25回開催された(2009年9月16日~2010年3月24日)。委員会では次の事項が検討された。
- 説明会、ワークショップの企画・運営
- 地域での活動状況の把握と地域への対応
- 活動に関する情報の発信と収集 (HPの運営)
- H22年度カリキュラムの作成
- 学習資源(調査機器、消耗品等)の調達
- 地域参加型学習支援センターが設置され、コーディネータ1名、事務担当者3名が雇用され、事業の運営および学生の地域活動への支援が行われた。
- 教員による地域視察と現地指導としては、豊根村(富山地区)、日間賀島、知多厚生病院、上矢作病院、名古屋市昭和区社会福祉協議会、名古屋市精神保健福祉センター、桜山商店街、瑞穂通商店街、向陽高校、桜山中学、松栄小学校について実施され、現地での情報収集、意見交換、学生指導が行われた。
4)事業に関する情報発信
- 医療系学部連携チームによる地域参加型学習」ホームページが作成され、公開された(http://www.med.nagoya-cu.ac.jp/amec/)
- プレスリリース
- 中日新聞夕刊1面(2009年11月20日)
- 女性なごや 1面(2009年12月20日)
- 大学広報誌等
- 医・薬・看連携教育ディレクタ(早野順一郎、浅井清文、木村和哲、飯塚成志、鈴木匡、前田徹、明石惠子. 医・薬・看連携チームラーニング:地域参加型学習の導入.名古屋市立大学大学院医学研究科・医学部広報誌「瑞医」10, 2009
- 医療系学部連携教育委員会(AMEC) 早野順一郎、浅井清文、木村和哲、鈴木匡、明石惠子、大原弘隆、前田徹、飯塚成志.文部科学省平成21年度大学教育・学生支援推進事業【テーマA】大学教育推進プログラム「医療系学部連携チームによる地域参加型学習」.名古屋市立大学広報誌「AGORA」1, 2010
- 医療系学部連携教育委員会、早野順一郎、浅井清文、木村和哲、大原弘隆、飯塚成志、鈴木匡、前田徹、明石惠子.「医療系学部連携チームによる地域参加型学習」がスタートしました.名古屋市立大学大学院医学研究科・医学部広報誌「瑞医」11, 2010.2
- 明石惠子、早野順一郎、木村和哲、浅井清文、鈴木匡、前田徹、飯塚成志.2009年度「医薬看連携早期体験学習」報告.名古屋市立大学看護学部紀要9;37-42,2010.3
- 医療系学部連携教育委員会(早野順一郎、木村和哲、浅井清文、飯塚成志、鈴木匡、前田徹、明石惠子.大学教育学生支援事業大学教育推進プログラムへの採択:医・薬・看連携チームラーニング:地域参加型学習の導入.名古屋市立大学薬友会会報59, 2010.3
- 高嶋悠、小笠原美沙、柳川亜由美.医薬看護学部連携早期体験学習に参加して:豊根村富山地区における地域医医療の現地調査.名古屋市立大学薬友会会報59, 2010.3
- 学会発表
- 河辺綾美、伊藤圭志、永田浩貴、水谷佳祐、小笠原美沙、高嶋悠、柳川亜由美、磯部菜津美、倉橋美紗乃、中西奈都美、浅井清文、木村和哲、鈴木匡、明石惠子、前田徹、飯塚成志、早野順一郎. 豊根村富山地区における地域医療の現状と課題、第60回名古屋市立大学医学会総会、名古屋市、2009.12.6
- 伊藤謙、北折侑里子、中谷優子、宮本駿、奥苑朱加、高見篤郎、山崎千鶴、伊藤里美、児玉温子、浪崎夏希、浅井清文、木村和哲、鈴木匡、明石惠子、前田徹、飯塚成志、早野順一郎. 篠島における地域医療の現状と課題. 第60回名古屋市立大学医学会総会、名古屋市、2009.12.6
- 前田徹、鈴木匡、飯塚成志、浅井清文、明石惠子、早野順一郎、木村和哲. 名古屋市立大学における医療人教育を志向した医・薬・看護学部連携早期体験学習への取り組み. 第19回日本医療薬学会年会、長崎市、2009.10.25
- 前田徹、飯塚成志、浅井清文、明石惠子、早野順一郎、木村和哲、鈴木匡. 地域に根づいた医療人教育を目指した医・薬・看護学部連携チームによる地域参加型早期体験学習の取り組み. 日本薬学会第130年会、岡山市、2010.3.28
2. 事業に対する地域および学生からの評価
平成21年度の本事業に関するアンケート調査が実施された。
1) 地域の協力者へのアンケート
- 対象 24地域38名、回答者30名 (回答率79%)
- 「ある程度そう思う」と「そう思う」の回答者数(割合)
- 学生は積極的に参加している。26名 (87%)
- 地域の活性化に有効である。20名 (67%)
- 医・薬・看3学部での合同の活動には意義がある。30名 (100%)
- ご自身は「地域参加型学習」の趣旨を理解している。27名 (90%)
- 運営体制・大学の対応は十分である。24名 (80%)
- この結果より、本年度の活動は地域での活動の準備、導入に留っており、効果は今後に期待する必要があるが、医・薬・看の合同の活動の意義は地域から高い評価が得られている。
2) 学生へのアンケート
- 対象 グループの代表者(またはメンバーの平均) 回答24グループ(100%)
- 「ある程度そう思う」と「そう思う」の回答者数(割合)
- 積極的に参加できた。23グループ (96%)
- 地域の活性化に有効である。16グループ (67%)
- 医・薬・看3学部での合同の活動には意義がある。18グループ (75%)
- 「地域参加型学習」の趣旨を理解している。19名 (79%)
- 大学の対応は十分である。16名 (67%)
- この結果から、今年度は任意参加であるためか、グループ間の活動状況の差が認められる。医・薬・看の合同活動に対する評価もグループ間で異なり、グループ内の協力状況に差が感じられる。
3) 学生からの活動状況報告
- 年度途中からの導入ということもあり、戸惑いも感じられるが、学生として自分たちにできることを懸命に模索している様子が窺われる。
- 地域とのふれあいの中で、関わりの難しさや限界も含めて、学生が多くのことを感じ、考える機会になっている点は評価できる。
- 学生の受け取り方に、この学習が良い経験になるようにしたいという積極的な姿勢が感じられる。
- 取り組みうる課題が、地域や施設の間でかなり異なる。その点をグループ間でどう調整し、さらに多様性を学習効果に活かすような工夫が、今後、大学に求められる。
3. 総括
年度途中からの導入で実質的な活動はこれからという感が強いが、活動の方向性としては、本事業の目標である「地域のニーズの発見と『学生なればこそできる』課題への取り組みを通じた課題解決能力の育成」に添った内容になっている。地域からも総じて理解と協力が得られつつあるので、今後、この取組が地域と大学教育の活性化に繋がることを期待したい。一方、対象地域や施設の多様性、学生間の協力状況の違いなどから、グループ間で活動のレベルや意欲に温度差が感じられる。教員は、地域と学生の双方にこの取組の趣旨と目的を浸透させると共に、学生グループの状況を常に把握し、適切な支援や指導を行うことで、それぞれのグループが意欲をもって取り組めるように努める必要がある。この取組が名古屋市立大学の教育文化のひとつとして地域に定着することを期待したい。
以上