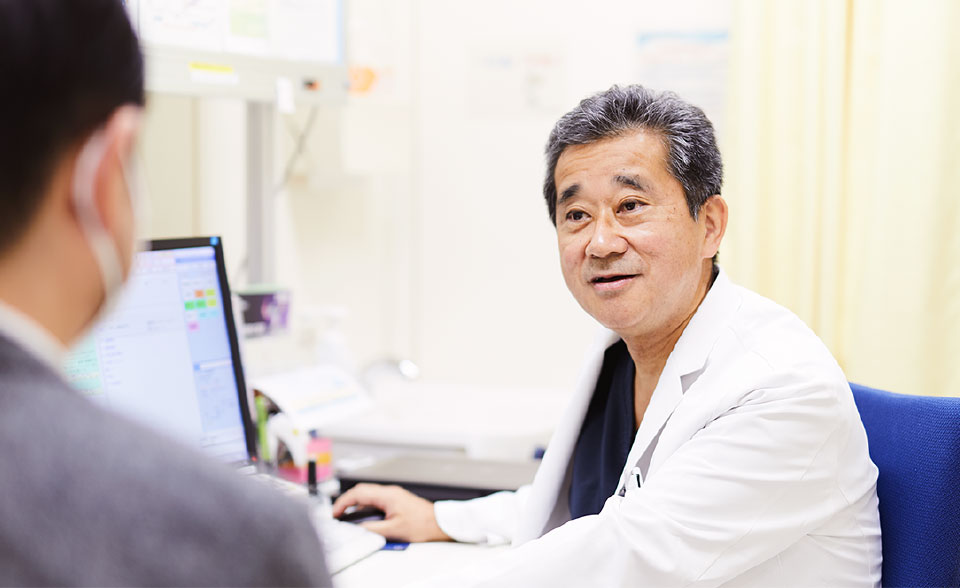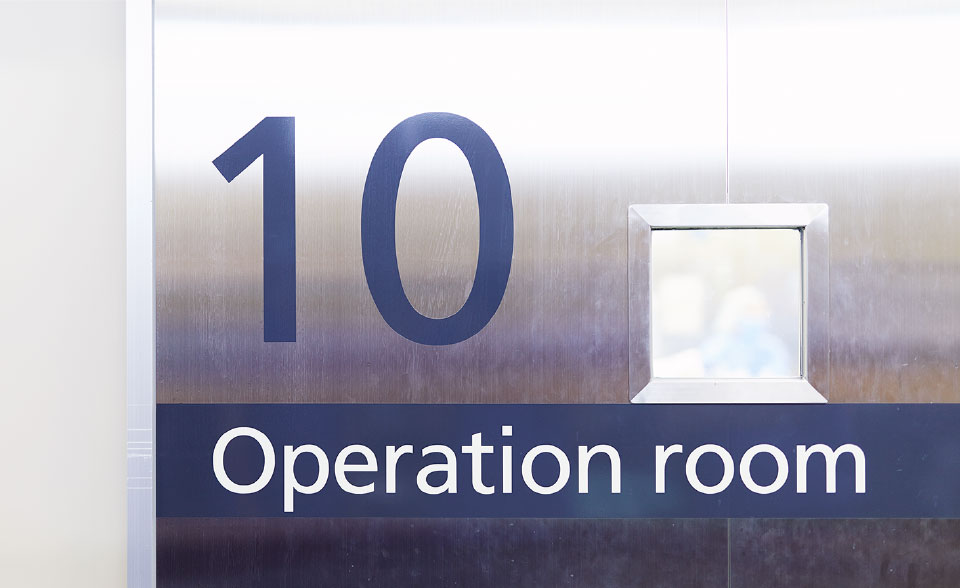手術を受けられる方へ
手術を受ける前に
・術前検査外来において血液検査、尿検査、胸部レントゲン検査、心電図検査、呼吸機能検査、鼻腔細菌検査を行い、耐術能を評価します。
・病気によってはCTやMRI,超音波検査、造影検査にて頭部や頚部の血管、冠動脈、下肢血管の状態の評価が必要になることがあります。
手術を受ける前に
大きく分けて、心臓手術には次の2種類があります。どちらの方法をとるかは患者さんの病気の種類によりほぼ決まっています。
【開心術】
心臓内部の操作が必要なために心臓を止めて行なう手術で、人工心肺を使用します。心臓弁膜症、胸部大動脈瘤、多くの先天心臓病の手術、などほとんどの心臓手術はこちらです。
【非開心術】
心臓表面あるいは心臓から出る血管(大動脈、肺動脈など)に対する手術で、心臓の拍動を止めずに行ないます。人工心肺補助下に行うことがあります。 たとえば先天性心臓病でチアノーゼのある子供に対する体肺動脈短絡手術や肺血流が増加している子どもに対する肺動脈絞扼術などがあります。 また、成人の手術では冠動脈バイパス手術は少し前まで心臓を止めて行なう開心術が主流でしたが、 最近では技術と道具の進歩により心臓を動かしたままで行なう事もあります。
- 心臓の内部、あるいは大動脈・肺動脈などを手術するには心臓を止めて心内を空にしたり、心臓から全身や肺に流れる血流を一時的に遮断する必要があります。
手術中、自分の心臓の代わりに酸素を含んだ血液を全身に送る機械を人工心肺装置といいます。
これは、①全身で酸素消費され心臓に還ってきた血液(静脈血)を太いチューブを用いて人工心肺装置に導き、②これを人工肺を用いて酸素を十分に含んだ血(動脈血)に変え、③その血液をポンプで太いチューブを介して大動脈から全身に送る働きをする装置です。
この装置を作動させることにより心臓を止めたり、肺への血流を遮断しても身体には酸素を十分に含んだ血液が流れ続けることができます。 - 心停止をさせるために心臓を栄養する血管(冠動脈)に心筋保護液を注入し、心停止させます。
また、手術操作の間に心臓の筋肉(心筋)が受けるダメージを減らすため、一定時間毎に心筋保護液を注入したり、心臓の周囲に氷水を入れて冷やします。 このような状態で心臓内部の操作(たとえば弁の手術や心臓内隔壁の穴の閉鎖など)や大動脈瘤の手術を行ないます。 - 必要な手術操作を終えたら、冠動脈に再度血液を流すことで注入されていた心筋保護液を洗い流し、心臓の拍動を再開させます。
しばらくして心臓の働きが十分回復したところで人工心肺装置を停止し、離脱します。時に心臓や肺の働きの回復が不十分で人工心肺から離脱することができない場合がありますが、 その際は一時的に補助人工心肺装置の使用を必要とすることがあります。 ①脳合併症(脳梗塞、脳出血)
開心術中の循環は生理的な循環と大きく異なりますが、たとえば動脈硬化(血管が硬くもろくなり内壁がボロボロになる病気)のためにもともと脳血管に狭い部分があった患者さんではそこから先の部分に血流不足がおこる危険性が考えられます。また血管内壁の破片が手術操作中に剥がれて脳血管に詰まる危険性もあります。いずれの場合にも血流不足に陥った脳は損傷を受け脳梗塞に陥ります。また、人工心肺回路内に発生した血の塊(=血栓)や空気がまぎれ込んだ場合などにもそれが流れていって脳血管を閉塞すると脳梗塞になります。このような事態を避けるためにさまざまな予防の工夫が行われていますが、完全になくすことはできていないのが現状です。また人工心肺内に血栓ができるのを予防するために多量に血をサラサラにする薬(=ヘパリン)を使用しますが、そのため出血傾向となり脳出血をきたすことがあります。
②術後の心不全
心不全というのは心臓の働きが低下している状態をいいます。手術時の人工心肺の使用や心停止に伴うストレスのため、術後には大なり小なり心不全の状態に陥ります。多くは利尿剤や強心剤を使用することで改善が期待できますが、それらの治療に抵抗する心不全の場合には補助人工心肺装置の使用が必要になる事があります。
③出血
心臓手術は血管や心臓を切ったり縫ったりする手術であること、上記のように人工心肺使用時に多量のヘパリンを使用するため出血傾向となること、血液が人工心肺装置を通る時に血液を固める成分(凝固因子、血小板)が破壊され、止血に難渋することがあります。
また、人工心肺装置のチューブを血管に差し込む時に大出血を生じることもあります。このような時には輸血が必要になります。
止血確認後に手術を終えますが、手術室を出た後に再び出血が始まることがあります。多くは輸血などで対応可能ですが、時に手術室に戻って止血術が必要になる場合があります。
したがいまして、術後は心臓の周りや胸の中に溜まった血液や水を体外へ排出するためにチューブ(=ドレーン)を一定期間留置します。
④不整脈
心臓手術の際には心停止の影響や心臓の刺激の通り道(=刺激伝導路)への直接的な傷害、心筋の興奮性の異常な亢進などにより不整脈が起こる事があります。
この結果、心臓の拍動数が極端に減少したり、逆に非常に速く打つことで心臓の働きが悪くなります。遅い場合には一時的(=体外式)ペースメーカーを用いて速く打たし、速い不整脈に対しては薬を用いて遅くします。
時に先天性心疾患の手術において、刺激伝導路に傷がつき心房からの刺激が心室へスムーズに伝わらなくなり、心房と心室がバラバラに収縮してしまうこと(=完全房室ブロック)があります。
その際は永久的な人工ペースメーカーを体内に植え込む必要があります。
⑤腎臓、肝臓、肺、その他の臓器障害
手術の影響は心臓、脳に限らず身体中のあらゆる臓器におよびます。特に人工心肺時間が長時間に及んだ場合や術後の心不全が高度の場合などに問題となります。
腎機能が低下して尿の産生が不良となり体内の老廃物が排出できない状態、すなわち腎不全になる事があります。その際は血液透析を行いながら腎機能の回復を待つことになります。
小児は血管が細く血液透析が困難のため腹膜透析を用います。これは、お腹の小切開から入れたチューブを使って腹腔に透析液を注入し、一定時間後にこれを排液することで透析液にしみ出てきた老廃物を体外に排出する方法です。
また、肝臓の働きが影響を受けて、黄疸を生じたり出血傾向が起こることもあります。特に術前から慢性肝炎や肝硬変のある患者さんでは術後に肝機能の低下が問題となる場合があります。
肺の合併症としては細菌による肺炎を生じたり、痰の排出が不良で肺の一部に空気の入らない部分を生じたり(無気肺)が起こる場合があります。
⑥創部感染症
細菌の侵入により創部が化膿して離開したり、手術で植え込んだ人工弁や人工血管、縦隔(心臓や大動脈を覆う空間)などに細菌感染を起こすことがあります(感染性心内膜炎、人工血管感染、縦隔炎)。人工血管感染や縦隔炎を来たすと抗生物質治療のみでは治療に難渋することが多いため、再手術やドレナージ手術が必要になることがあります。手術時に感染予防のために抗生物質を使用していますが、患者さん自身の皮膚にひそんでいる細菌を根絶することができないことや、患者さんの抵抗力が術前の心不全状態で低下しているうえに心臓手術という大きなストレスのためにさらに落ち込んでいること、などから感染をきたしてしまうことがあります。
【集中治療室】
多くの患者さんは手術直後は人工呼吸を行いながら集中治療室へと向かいます。
集中治療室では麻酔科医、集中治療医が主に循環、呼吸などを中心とする全身管理を行っていますが、手術直後は後出血を来たすことがあり注意が必要です。
特に手術の当日および翌日は循環や呼吸機能の変動が激しく、急を要する処置や管理を必要とすることが多いため患者様のご家族には院内待機をお願いすることがありますのでご協力をお願いいたします。
入室中の面会時間は11:00~12:00と18:00~19:00の1日2回、各1時間になります。この間に心臓血管外科主治医または当番医、麻酔科、集中治療医より病状説明があります。
循環や呼吸状態が安定して、人工呼吸器から離脱を行い、状態が安定した時点で一般病棟へ帰室します。
【一般病棟】
①点滴、酸素
一般病棟では術後の心不全治療、呼吸状態の改善を中心に治療を行います。点滴の強心剤や利尿剤も内服へと移行し、点滴投与を徐々に減らしていきます。また酸素吸入を行っている場合は吸入酸素濃度を徐々に減らしていきます。先天性心疾患のお子さんは退院後も酸素を必要とすることがあるため、その際は在宅酸素療法(HOT)を行います。
②ドレーン
術後は心臓の周りや胸の中に溜まった血液や水を体外へ排出するために管(=ドレーン)を留置してくるため、出血や水の量が減ってきたらこれを抜去します。
③創部
必要な場合は術後1週間~10日頃に抜糸を行いますが、創部の接合が不良な場合は再縫合を行うことがあります。
入浴は創部が完全に治癒したと判断した時点から可能になります。
④術後評価
術後は適宜、血液検査やレントゲン検査、CT検査などを行います。
術後の心機能評価のため心臓超音波検査、その他の諸検査で問題がなければ近日退院となります。
⑤その他
心臓の手術を受けられる患者様は術後に一時的な水分制限が必要となることがあります。
心臓の状態が安定してきたら徐々に水分制限を緩和していきます。
胸骨を縦に切って行う手術の場合には術後、胸骨の骨癒合が得られるまでの約2カ月間は胸骨離開、膨隆を予防するために胸帯を着用していただいています。その間は前胸部に強い衝撃を受けないようにしてください。