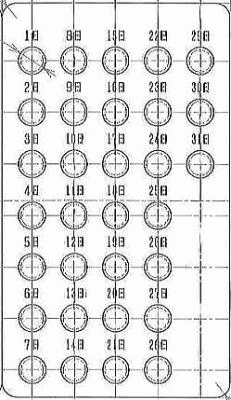研究者自主研究として、東洋人におけるアスピリン腸溶錠(1錠100mg/day)による大腸がん予防効果を二重盲検無作為割付臨床試験により評価する
(1) 対象条件
大腸に大腸腫瘍(粘膜内癌・腺腫)を1個以上持ったことのある40歳以上、70歳以下の患者である。
(2) 試験薬
低用量アスピリン(100mg/day)腸溶錠またはプラシーボ錠を1日1錠服用する。
2年間試験薬を投与する。
(3) 主な評価項目 ・大腸内視鏡検査(服用開始前、服用開始2年目)
・食事調査、生活習慣アンケート(開始時)
・直腸粘膜のACFの観察と評価(札幌医科大学第4内科のみ:60例)
・S状結腸粘膜のmRNA(Cyciln
D1、PCNA、Baxなど)測定(大阪中央病院のみ:200例)
・2年目の大腸内視鏡検査が終了後、その後2年から3年後に大腸内視鏡検査で追跡
(4) 予定参加者数 試験参加人数700人、最終解析人数500人(1群250人)を目標数とする。
(5) 研究期間
| 登録期間 | : | 2006年7月1日~2007年12月31日(18ヶ月間) |
| 試験薬投与期間 | : | 2年間 |
| 試験実施期間 | : | 2006年7月1日~2012年12月31日 |
| 追跡期間 | : | 最終患者投与終了後3年間 |
(6) 中間解析
中間解析は実施しない。
| 大阪警察病院 | : | 36人 | 広島市民病院 | : | 30人 | |
| 豊橋市民病院 | : | 40人 | 三重県立総合病院 | : | 5人 | |
| 三重大学消化器外科 | : | 5人 | 東邦鎌谷病院 | : | 40人 | |
| 愛知がんセンター中央病院 | : | 40人 | 昭和大学横浜市北部病院 | : | 30人 | |
| 産業医科大学 | : | 18人 | 広島大学病院 | : | 30人 | |
| 木村病院 | : | 40人 | 神戸掖済会病院 | : | 10人 | |
| 東住吉森本病院 | : | 40人 | 守口敬任会病院 | : | 10人 | |
| 北里大学医学部外科 | : | 10人 | 名古屋市立大学臨床機能内科 | : | 20人 | |
| 市立堺病院 | : | 30人 | 大阪大学医学部消化器内科 | : | 10人 | |
| 国立がんセンター中央病院 | : | 40人 | 国立がんセンター東病院 | : | 40人 | |
| 杉本憲治クリニック | : | 20人 | 札幌医科大学第4内科 | : | 60人 | |
| 大阪中央病院 | : | 200人 |
― 2.背景 ―
本邦における大腸癌の発生率は急激に増加しているため、発癌を予防する研究は重要な課題である。
これまでにも、われわれは食事指導や生活指導、食品成分の投与などによる臨床試験を行い、多くの大腸癌予防に関する知見を得てきたが、それらによる予防効果は比較的軽度であった。そこで今回は、薬剤を用いたさらに強力な大腸癌予防法の開発を研究の目的とした。試験で用いる発癌予防候補薬剤の選定について系統的に絞り込んでから、臨床試験を企画した。
まず、終了または実施中の大腸癌予防臨床試験の報告を収集し、発癌予防候補薬剤を列記した。それらの薬剤の作用仮説、メリット、デメリット、特徴などを整理した資料を作成し、専門家による検討会により候補薬剤の絞り込み、最終的に1剤を予防薬剤として決定し、その後、必要症例数などの算出、実施施設の選定、参加呼びかけ手順などを検討した。
予防薬剤として、各種のサイクロオキシゲナーゼ2選択的阻害剤を含む非ステロイド系抗炎症剤、ウルソデオキシコール酸、5アミノサルチル酸、カルシウム製剤、塩酸ピオグリタゾン、葉酸など多数の薬剤が候補としてあげられ、それらの物質に関して、論文のレビューを行い数回にわたる検討会を実施した。ウルソデオキシコール酸や5アミノサルチル酸は作用仮説の根拠が不十分であること、カルシウム製剤はこれまでの成績では抑制効果が弱いこと、塩酸ビオグリタゾンは臨床投与経験が少ないこと、葉酸は食事からの摂取量が欧米に比して本邦では多いと考えられることなどより、アスピリン腸溶錠(100mg)1日1錠投与と決定した。
心疾患の予防のためにアスピリンを5年間325mg隔日投与した二重盲検無作為割付臨床試験1)では、アスピリンの投与により心疾患は予防できたが、大腸癌や腺腫の発生は予防できず、大腸癌を予防するためには、アスピリンの量を増やすか、投与期間を延長する必要があると結論づけている。最近になり、本試験と類似したアスピリンを用いた大規模臨床試験の結果が2つ報告された。一つは、1121人の腺腫の既往を持つ患者を対象に、プラセボ群、アスピリン1日81mg投与群、アスピリン1日325mg投与群の3群に分け、3年間介入を行う臨床試験2)である。腺腫の発生状況は各群で差はなかったが、悪性度が高いと考えられる病変(1cm以上、絨毛状腺腫成分を持つもの、severe dysplasiaや浸潤癌)の発生に関しては、81mg投与群で相対危険度が0.59と有意に減少した。しかし、325mg投与群では相対危険度は0.83とそれほど減少しておらず、用量相関は見られなかった。もう一つの試験は635人の大腸癌術後の患者を対象にプラセボ群とアスピリン325mg投与群に分けて介入する臨床試験3)である。介入期間の中央値が12.8カ月の時点で、新たな腺腫がプラシーボ群では27%で発見されたのに対し、アスピリン群では17%と有意に少なかった。しかし、累積発生率でみると、1年目のところまでは累積発生率に差が広がるものの、1年目以降はプラセボ群とアスピリン群は、ほぼ並行して増加しており、アスピリンを長期間投与したときの効果については疑問が残る。このようにアスピリンによる大腸腺腫発生予防効果についてはいまだ評価は定まっていない。1日にアスピリン100mgでは、欧米の臨床試験の結果からは投与量は不足とも考えられるが、日本人は欧米人に比して非ステロイド系抗炎症剤による胃腸傷害が強い可能性があること、本邦では大規模な臨床試験は行われていないことより、本試験は実施する価値があると判断し、試験を企画した。
― 3.目的 ―
研究者自主研究として、東洋人におけるアスピリン腸溶錠(1錠100mg/day)による大腸がん予防効果を二重盲検無作為割付臨床試験により評価する― 4.対象者条件 ―
(1) 対象条件下記のすべての条件を満たす者を対象者とする
・組織診断で確診された大腸腫瘍(粘膜内癌・腺腫)を1個以上持ち、それらすべてを 内視鏡的に摘除できた者(摘除時期は問わない)
・大腸腫瘍の内視鏡的治療歴(組織診断を含む)がすべて判明している者
・これまでに全大腸内視鏡検査を2回以上受けた者
・全大腸内視鏡検査にてクリーンコロンを3カ月以内に確認した者
・40歳以上、70歳以下(性は問わない)
※ クリーンコロンの定義
全大腸内視鏡検査にて、内視鏡的に腫瘍性病変(腺腫、癌)を認めない状態。もしも、内視鏡的に腫瘍性病変を認めた場合でもその場で内視鏡的に完全摘除できればクリーンコロンとする。4mm以下の病変に関しては、通常生検による処置でも内視鏡的に消失を確認できれば完全摘除とする。
内視鏡的に過形成性ポリープ、炎症性ポリープであることが明らかな場合は、生検による確認は必要ない。
(2) 除外基準
・粘膜下浸潤(sm)以深の大腸癌の既往を持つ者
・現在、アスピリン(商品名:バイアスピリン、バッファリンなど)、塩酸チクロピシン(商品名:パナルジンなど)、ワーファリンカリウム(商品名:ワーファリン)、ジピリダモール(商品名:ペルサンチン)などの抗凝固剤、抗血栓剤を服用中の者
・脳卒中(一過性脳虚血発作:TIAを含む)の既往者
・大腸切除者(虫垂切除は参加可能)
・家族性大腸腺腫症患者
・胃潰瘍、十二指腸潰瘍の治療既往者
(ヘリコバクターピロリの除菌成功者でその後、潰瘍のS2治癒が確認できている者は 参加可能)
* 胃潰瘍・十二指腸潰瘍治療既往者でないことの確認方法
問診で胃潰瘍、十二指腸潰瘍の既往を確認してそれらの既往がないこと
現在、空腹時痛などの症状のないこと
最も近い時期での上部消化管内視鏡検査または上部消化管造影検査の所見をな
るべく把握する
・炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)、出血性憩室炎、高度の出血性胃炎など
の易出血性疾患を合併している者
・出血傾向のある者、血小板数10万以下、PTの異常値者
・参加時点で、癌を持っている者
・アスピリンに対してアレルギーの既往のある者
・抗がん剤を使用中の者
・妊娠中及び試験期間中に妊娠予定のある者
・処方箋薬、OTC薬を問わず、痛み止めなどのため非ステロイド系抗炎症剤(NSAIDs)を週3回以上服用している者
※ 上記条件以外でも、アスピリン(商品名:バイアスピリン)取扱説明書にて慎重投与と されている下記の条件に合致する者への参加呼びかけは慎重に行うこと。
・肝障害又はその既往歴のある患者
・腎障害又はその既往歴のある患者
・気管支喘息のある患者
・アルコールを常飲している患者
※) 言葉の定義
「対象者」上記条件に合致する者
「参加者」上記条件に合致して、インフォームドコンセントを得て、試験に参加した者
― 5.説明と同意(インフォームドコンセント) ―
(1) 説明各施設の試験担当者が、面談により対象者本人へ下記の内容を詳しく説明する。説明・同意文書は、説明するときに対象者本人に手渡す。
・この臨床試験の目的
・この試験で服用する薬は、アスピリン腸溶錠(1錠100mg)またはプラシーボであること
・どちらを受けるかは、無作為(ランダムに決める方法)で決められること
・アスピリンの摂取において考えられる副作用。
・この臨床試験への参加は自由で、参加しなくても不利益を受けないこと
・この臨床試験への参加に同意した場合でも随時これを撤回できること
・より有効な治療法が判明した場合について
・個人情報は大阪市内に設置された事務局が管理するが、プライバシーや医療記録は 守秘されること
(2) 同意の取得
説明を行い、対象者がこれらの試験の内容をよく理解したことを確認した上で、試験への参加を依頼する。対象者が試験参加に同意した場合は、説明文書に自署による署名を得る。
(3) 同意取得時期
同意の取得は登録の前とする。
(4) 同意書の保管・管理
同意書は各施設が保管する。参加者本人に説明文書および同意書のコピーを手渡す。
― 6.試験方法 ―
(1) 試験の手順1) 各施設の担当者は、全大腸内視鏡検査を3カ月以内に実施された対象者を診察した場合、「登録適格性確認票」のチェックリストを用いて、適格か否かを判断する。
2) 適格条件を満たした場合、各施設の責任者は対象者に本試験の存在を説明し、参加同意を得る。
3) 「ケースカード(エントリー時)」に必要事項を記入する。
4) 参加者の割付員因子(施設、性、年齢(60歳未満/60歳以上))を試験統計家に連絡し、事務局が割付番号を受ける。事務局は各担当医師に連絡をする。
5) 担当医師は割付番号の記載された試験薬を3カ月から6カ月分手渡す。
・PTPシート1枚に31錠の試験薬が入り、次月の1日より服用を開始する。
・次回の診察までの期間分を手渡す。最長6カ月とする。
・事務局に「J-CAPP Study参加者資料」を郵送し、連絡用登録番号を得る。
6) 参加者は、1カ月毎に服用日誌と服用したPTPシートを事務局に郵送することにより、事務局は服用状況を把握する。
7) 定期的に受診し、次回受診日までの試験薬を手渡す。
8) 2年目に大腸内視鏡検査を行い、所見を2年目の「ケースカード(終了時)」に病状把握用登録番号で匿名化して記入する。
・2年目の大腸内視鏡検査は試験薬服用開始から1年9ヶ月後以降2年3カ月までに実施する。
・大腸内視鏡検査の術者名を記録する。
・大腸内視鏡検査など出血の危険性のある検査の1週間前から試験薬の服用は休 薬する。
※ 試験薬服用前の大腸内視鏡検査にて検体採取などが必要な場合の対応について エントリー予定の500人中、直腸のACFを測定する60人(札幌医科大学第4内科担当)と、S状結腸のmRNA採取を行う200人(大阪中央病院担当)は、試験薬服用前大腸内視鏡検査でmRNA採取やACFカウントが必要なため、検査前にそれらの測定が行われている者を対象者の条件に追加する。
※ 個人情報の管理について
試験参加者の個人情報(名前、住所、電話番号、通院施設、試験開始日時、個人連絡用登録番号)は、試験精度維持のため、京都府立医科大学分子標的癌予防医学大阪研究室内に設置された事務局で管理し、1カ月毎の服用状況の把握、大腸内視鏡検査の受診勧告、有害事象の早期発見のため、参加者と連絡を取り合う。
データセンターの作業は、有限会社メディカル・リサーチ・サポートが事務局内に出向して行う。個人情報保護のため、参加者の個人情報にアクセスできる担当者を限定し、立ち入りが限定される部屋の鍵のかかるキャビネットに資料は保管され、データはインターネットとつながらないコンピューターのみに保存する。担当者とは秘密保持の契約を結ぶ。参加者には、データセンターの住所や個人情報にアクセスできる担当者名を公開する。
なお、割付の際には、個人情報は用いず割付因子を試験統計家に通知し、割付結果が各施設に送られるため、個人情報は外部に出ない。
参加同意取得後、個人情報を記入、その用紙がデータセンターに封書郵便で送られ、データセンターにて厳重に管理される。データセンターでは、参加者への連絡のみに個人情報は使用され、データセンターから個人情報は移動しない。
個人情報を含む文書等は、必ず封書による郵便を用い、FAX、E-mailは用いない。
※ 個人情報管理に関わる組織構成
| 試験責任者 | : | 鈴木貞夫(名古屋市立大学医学部) |
| 事務局 | : | 石川秀樹(京都府立医科大学 データセンター監督責任者) |
| データセンター(メディカル・リサーチ・サポート) | ||
| : | 大谷透、那須綾子、佐伯智子、青山智子、清水正子 | |
| 管理栄養士 | : | 中村富予、竹山育子(京都府立医科大学) |
| 試験統計家、他施設共同研究者、倫理モニタリング委員会は、個人情報を把握しない | ||
※事務局が個人情報を管理する理由
1) 臨床試験精度が向上する
服用状況について、1ヶ月ごとの服用日誌、PTPシート回収により確実な把握が可能となる。
2年目の内視鏡検査前に受診勧告を行うことにより、確実なエンドポイント把握が可能となる。
毎月のニュースレター送付により、参加者の受容性向上が得られる。
2) 有害事象の把握が確実、迅速になる
参加者に何かの変化があったとき、24時間いつでも連絡のできる事務局(窓口)が確保できる。平日9時から5時は事務担当者、それ以外の時間は試験実務担当医師の石川秀樹の携帯電話に連絡が取れるようにしている。
1ヶ月ごとの服用日誌のやりとりで、軽微な変化の把握が確実にできる。
| 事務局 : 京都府立医科大学 分子標的癌予防医学 大阪研究室内 J-CAPP Study 事務局 住所 〒550-0003 大阪市西区京町堀2-3-1-2F 電話 06-6445-5585 |
3)試験担当医の負担軽減
試験担当医は、参加呼びかけ、外来での試験薬手渡し、次回診察予約、2年目内視鏡検査予約、内視鏡検査実施に専念できる。
(2) 登録場所
登録場所は各施設にて行う。登録情報は事務局で管理する。
(3) 割り付け方法
割付方法は、試験統計家が、施設、性、年齢(60歳未満・60歳以上)を割付因子とした層別化ブロックランダム法により、無作為にアスピリンを服用するアスピリン群と、プラシーボを服用するプラシーボ群に分ける。割付方法は、別途、手順書(本手順書は試験実施者にもブラインドにするため、公表できない)に従い実施する。
(4) 予防方法と経過観察
参加者は試験薬を、1日1回、1錠を食後に服用し、服用日誌に服用状況を記入する。服用時期は、朝食後、昼食後、夕食後のいつでも良いこととする。ただし、前日に飲み忘れた分を翌日、まとめて2錠は服用しない。
1ヶ月ごと2年間、事務局より参加者に返信用封筒と翌月の服用日誌、ニュースレターを送付する。服用した前月のPTPシート(服用忘れの錠剤を含む)、前月の服用日誌を返信用封筒に入れて事務局に送り返す。このように参加者と事務局は定期的な連絡を取り合い、受容性を確認する。もしも、服用できていなかったり、問題が発生したりした場合には、速やかに各施設の責任者に連絡する。有害事象急送の必要のある事項については、速やかに各施設の責任者に連絡し、各施設の責任者より有害事象報告を行う。
服用状況などについては、なるべく速やかに各施設の責任者に報告する。
(5) 試験薬の休薬、中止、中断
有害事象が発生した場合、その都度、各施設の責任者は「有害事象報告書」に必要事項を記入し、事務局にFAXする。事務局は追加事項を記入の上、FAXを試験統計家に転送する。試験統計家は割付内容を記載する。
【試験薬の休薬、中止】試験薬に由来する可能性のある有害事象が発現した場合には、各施設の責任者の判断で一時休薬し、症状の改善を確認してから投与を再開する。投与再開により有害事象が再現される場合には投与を中止する。ただし、重篤な有害事象が出現し、試験継続が困難と判定された場合には直ちに投与を中止する。これらの事象が発生したときには、各時点で逐一事務局に連絡する。
有害事象の具体例としては、脳出血、吐血、下血、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、貧血、死亡、アレルギーなどであるが、明らかに基礎疾患が原因と考えられた場合でも、試験期間中にこれらの事象がみられたときには、有害事象として報告する。
重篤な有害事象の基準はJCOGのグレード分類を採用、3以上を重篤な有害事象とする。
本試験参加中に癌が診断された場合、その参加者の試験は中止とする。
本試験参加中に胃穿孔など手術が必要な場合には直ちに投与を中止する。
循環器疾患などで抗血栓剤、抗凝固剤の服用が必要になった場合には、試験参加を中止し、通常保険診療として抗血栓剤を投与する。
参加者が試験の中止を希望した場合は、中止とする。ただし、参加者本人の意思による本試験参加への同意撤回により試験薬の服用を中止した場合でも、参加者の了解が得られればintent to treat(ITT)解析を行うために大腸内視鏡検査は実施する。
【試験薬の中断】試験データの使用や2年目の大腸内視鏡検査受験を参加者が了解しなかった場合のみ中断とし、ITT解析には含めない。
試験参加中に脳出血や吐血などが発生した場合には、誠意を尽くして、最大限の医療を行う。
(6) 併用療法、後治療
1) 本試験期間中、疾患の治療は通常と同様に行う。
2) 本試験期間中は試験薬以外の抗凝固剤、抗血栓剤(商品名:バイアスピリン、ワーファリン、パナルジンなど)は服用しないように指導する。
3) 頭痛薬、解熱剤(OTC薬を含む)の服用はなるべく控えるようにするが、もしも、服用した際には、服用日誌に記入することとする。
4) 症状等に応じて、制酸剤などの胃薬の投与は行ってよい。
5) 有害事象に対する対症療法は行ってよい。
6) 合併症に対する治療は行ってよい。
7) 腺腫などの発生後の治療は最善の治療を行う。
(7) 追跡調査
服薬終了時2年目の大腸内視鏡検査が終了後、その後2年から3年後に大腸内視鏡検査を実施して、その結果も把握する。その大腸内視鏡検査までは、アスピリンの服用はしないように指導する。その後も参加者の了解が得られれば、可能な限り大腸内視鏡検査結果を把握する。
― 7.試験薬 ―
| 使用する試験薬は以下の通りである。 | ||
| メーカーはBayer HealthCare(ドイツ本社) | ||
| PTP包装は、マルホ発條株式会社に依頼、両面アルミ包装 | ||
| 袋詰め担当者 | : | 石川秀樹、那須綾子、佐伯智子、青山智子、鈴木貞夫 |
| 作業責任者 | : | 石川秀樹 |
| 袋詰めはマルハ発條のPTP包装作業室で行い、作業終了後の管理は事務局にて行う。 | ||
(1) アスピリン(100mg/day)腸溶錠(Lot number:05623804)
別紙、低用量アスピリン腸溶錠(商品名:バイアスピリン)インタビューフォーム参照のこと。
(2) プラシーボ錠(Lot
number:06170412)
アスピリンを含まず、外観上、アスピリン腸溶錠と見分けのつかない錠剤である。
これらの試験薬は、各施設の試験担当医師が、個人の責任において、ドイツのバイエル本社より個人輸入を行った。通関の際には薬鑑証明を取得し、各施設の試験担当医師が試験薬の管理を行う。
― 8.症例の登録方法 ―
試験統計家の名古屋市立大学公衆衛生学教室、鈴木貞夫が症例の登録、割付を管理する。実務の登録はデータセンターにて行う。
― 9.検査および評価項目 ―
(1)大腸内視鏡検査(服用開始前、服用開始2年目)
・試験開始時と終了時に全大腸内視鏡検査を実施し、大腸病変の有無を確認する。もしも、隆起性病変があった場合には、生検または内視鏡的摘除による組織診断を実施する。
・内視鏡検査時にS状結腸の2カ所より大腸粘膜採取し、mRNAの抽出を行う(大阪中央病院のみ)。
・内視鏡検査時に直腸のACFを計測する(札幌医科大学第4内科のみ)。
・内視鏡検査は保険診療にて実施する。
(2)血液検査(服用開始時)
・必須項目:PT、末梢血球数(試験薬投与開始までに測定する)
内視鏡検査前に必ず測定する必要はないが、試験薬投与前には必ず確認する。
・内視鏡実施前に測定があれば記入する項目:AST(GOT)、ALT(GPT)、γGTP、尿酸、T-Chol、HDL-Chol、中性脂肪
・可能な範囲で、1年目、2年目の貧血検査を行う。
(3)食事調査、生活習慣アンケート(開始時)
・名古屋市立大学公衆衛生学教室にて作成した自記式食事摂取頻度票(FFQ)にて食事内容を把握する。
・生活習慣に関するアンケートを実施する。
(4)服用内容の認識の確認(1年目、2年目)
・参加者に、自分はアスピリンとプラシーボのどちらを服用していると思っているかを尋ねる。
これは、二重盲検試験が成功しているかどうかを確認するために行う。
(5)ACFの観察と評価(札幌医科大学第4内科のみ:60例)
ACFの観察は、大腸拡大内視鏡(Fujinon-Toshiba
ES システム, EC485ZW)を用いて、既報4)に従い行う。すなわち、拡大内視鏡を用いて全大腸内視鏡検査を施行した後、下部直腸領域(歯状線~第2ヒューストン弁)に0.2%メチレンブルーを散布し、ACFを観察する。同領域におけるACFの数、大きさ、dysplasiaの有無を評価する。尚、ACFの大きさは既報に従いクリプトの数が10個未満をsmall、10個以上20個未満をmedium、20個以上をlargeとする。
薬剤を半年間(5~7ヶ月)投与したところでsigmoidoscopy(SF)を行い、ACFの評価を行う。2年後に全大腸内視鏡検査を行い、ACF及びポリープの評価を行う。
(6)mRNA
肛門から20cmの内視鏡的に正常と考えられるS状結腸粘膜を2個生検採取する。近傍に腫瘍がある場合には、生検部位は、腫瘍から5cm以上離し、血管、リンパろ胞をさける。生検組織は、1個で平均湿重量約5mg回収できる。生検直後に検体はRNAlaterTM(RNA
Stabilization Reagent;Qiagen GmbH)に浸透させ冷所で保管、当日にmRNAを抽出する。mRNA発現量の測定はリアルタイムPCR法にて行う。抽出したRNAは逆転写反応によりcDNA
(complementary deoxyribonucleic acid)を合成した後、リアルタイムPCR法によりmRNAの定量を行う。
測定するmRNAはCyciln D1、PCNA、Baxである。知見の増加により、測定項目を増やす可能性がある。
― 10.予想される有害反応 ―
(1) アスピリン腸溶錠
消化管粘膜傷害(胃痛、胃部不快感、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、小腸潰瘍)や出血傾向に起因する疾患(脳出血、吐血、下血、貧血)などが考えられる。重大な副作用(頻度不明)としてショック、出血、皮膚粘膜眼症候群、再生不良性貧血、喘息発作がある。
アスピリン腸溶錠100mgの心血管疾患および脳血管疾患予防のための投与におけるドイツでの市販後調査試験において、調査症例2,739例中、副作用発現症例数は73例(副作用発現件数は87件)であり、副作用発現率は2.67%(73/2739)であった。
副作用の内訳では、消化管障害(胃炎,消化管出血,潰瘍等)が最も多く2.63%で、出血・凝血障害(血腫1人、血栓性静脈炎1人、網膜出血1人、鼻血1人の合計4人)0.15%、過敏症(発疹)0.07%、精神神経系障害(めまい)及び血液障害(貧血)はいずれも0.04%であった。
低用量アスピリンを服用していなくても、脳出血を発症することはあり得るが、本試験で用いる低用量アスピリンと同じ薬を用いた心疾患の臨床試験の集計(低用量アスピリン群5476人、対照群5507人)では、脳卒中の既往者では、低用量アスピリンを服用しても脳出血の頻度(低用量アスピリン群0.20%、対照群0.25%)は増えなかった5)。
詳細はインタビューフォーム、低用量アスピリン腸溶錠(商品名:バイアスピリン)(添付資料を参照のこと)。
(2) プラシーボ
特になし。
(3)大腸粘膜生検(大阪中央病院のみ)
生検により、出血の可能性が考えられる。
石川らの大阪府立成人病センターにおける経験では、インフォームドコンセントを得て実施された1,000件以上の同様の正常粘膜の複数個にわたる生検検査にて、処置を必要とする出血は1回も経験していない。
- 11.エンドポイント、予定症例数とその算定根拠、症例集積期間 -
(1) エンドポイント
主エンドポイントは、2年目の大腸内視鏡検査における新たな大腸腫瘍(腺腫、癌)の発生の有無である。
副エンドポイントは、試験期間内の有害事象発生率、他臓器癌の発生の有無、2年目の大腸内視鏡検査における新たな大腸腫瘍の大きさ・個数・組織(異型度、絨毛状腺腫成分の有無;組織診断は境界病変については検体を集めて中央判定する)、介入後2~3年後の大腸腫瘍発生状況、直腸粘膜のACF数(札幌医科大学第4内科のみ)、S状結腸粘膜の大腸癌関連蛋白のmRNA発現程度(大阪中央病院のみ)である。
(2) 予定参加者数
700名の試験参加を目標とする。
参加募集期間内でも、予定参加者数に到達すれば、募集を終了する。
(3) 参加者数算定の根拠
過去の本邦での報告では、複数の大腸腺腫を内視鏡的に切除した者の2年目内視鏡における腫瘍発生率は約60%である。単数の大腸腺腫患者も含めると40~50%の発生が考えられる。2003年のNEJMの論文では、プラシーボ群での腺腫発生率は13~27%である。
同報告では、アスピリンの投与によりポリープの発生はプラシーボ群に比して約60%に減少している。
アスピリンの腺腫発生率抑制効果を発生率比で0.6と想定し、両側有意水準5%の検定を実施したとき、80%の検出力を確保することができるのは、1群当たり、下表の通りである。
<アスピリンの腺腫発生抑制効果0.6>
| プラシーボ群発生率 | アスピリン群発生率 | 1群当たり必要症例数 |
| 25% | 15% | 250人 |
| 40% | 24% | 152人 |
| 50% | 30% | 93人 |
以上より、1群で約250人、合計約500人を目標とする最終解析人数とした。ITTにより解析を実施するため参加同意者を700人とした。
(4) 参加者登録期間
2006年7月1日~2007年12月31日(18カ月間)
(5) 試験実施期間
2006年2月1日~2012年12月31日
(6) 追跡調査期間
最終患者投与終了後3年間
― 12.データの集積及び解析 ―
(1) 有効性評価のための大腸腺腫発生の定義
試験薬服用2年目に全大腸内視鏡検査を実施する。できる限り前処置は経口腸管洗浄法を採用する。
隆起性病変を認めた場合、生検検査、hot biopsy(生検鉗子にて病変部位を保持し、高周波電流を通電し焼却する治療法)、内視鏡的粘膜切除術などを用いて、組織採取を行う。ただし、明らかに過形成性ポリープまたは炎症性ポリープと判断された場合には、組織採取は行わない。
・過形成性ポリープ、炎症性ポリープの診断
1) 拡大内視鏡による観察でピットパターンが工藤のⅠ型(腺管口が円形)またはⅡ型(腺管口が星状)
2) ある区域に通常観察で過形成性ポリープまたは炎症性ポリープと考えられる隆起性病変が複数存在する。
*通常観察で過形成性ポリープと考えられても、単発の場合には、組織診断を実施する。
(2) 患者及びデータの取り扱い
適格条件を満たした全ての登録患者を本試験の対象とし、大腸腫瘍(腺腫、がん)発生のみをイベントとする。
大腸以外の臓器の腫瘍(腺腫、がん)の発生は副エンドポイントとする。
追跡期間中に他病死、及び事故などの例外的な他因死については、死亡の時点で打ちきりとして扱う。
追跡不能例は、脱落時点で打ち切りとして扱う。
(3) 統計解析
1) 登録状況の集計
毎月、データセンターにて登録状況の集計を行い、データセンター便りとして、試験関係者にメールで送付する。有害事象などが発生した場合や、試験薬に関する新たな情報が得られた場合も、参加者全員にメールで報告する。
2) 試験薬服用効果の評価
評価は主要評価項目である大腸腫瘍発生に関して、「患者及びデータの取り扱い」に従い主たる解析と補助的な解析を行う。主たる解析はintent-to-treat(ITT)の原理に基づき、全登録患者を対象とした解析を一義的に行う。
試験データの使用や2年目の大腸内視鏡検査受検を参加者が了解しなかった場合のみ中断とし、ITT解析には含めない。
また、割り付けられた試験薬の服用が正しく開始された患者のみを対象とした解析も同時に行う。
3) 安全性の解析
安全性は群毎の有害事象の発現頻度を算出し、その発現率に関して群間差の両側95%信頼区間を求める。なお、発現率がある程度大きな症状・所見に関しては、その事象が起きることをイベントと考えたKaplan-Meier法により累積発現率を計算し、必要に応じてlog-rank検定を行う。また、重篤な有害事象については、試験薬との因果関係別及び発現時期別の集計も行う。
4) 有害事象への対応
有害事象がきわめて本研究において重大であると考えられたとき、または有害事象の発生がアスピリン群に偏って起こる確率が、有害事象の発生率が両群共に等しいという仮説が20%以下の危険率で棄却された場合、試験統計家は倫理モニタリング委員会委員長に直ちに報告する。倫理モニタリング委員会委員長は倫理モニタリング委員会を至急開催し、協議を行う。
(4) 中間解析
中間解析は実施しない。
― 13.モニタリング ―
別紙、倫理モニタリング委員会実施要項に従い、定期的なモニタリングを実施する。
― 14.研究成果の発表 ―
本試験計画に基づいて実施された研究成績は後述の共同研究者全員のものとし、本研究に参加した研究者の合意のもとに公表する。
― 15.研究組織 ―
<施設責任者とエントリー施設、エントリー予定数(エントリー期間18カ月)>
| <敬称略:順不同> | ||
| 阿部孝 | (大阪警察病院) | ・・・ 36人 |
| 水野元夫 | (広島市民病院) | ・・・ 30人 |
| 岡村正造 | (豊橋市民病院) | ・・・ 40人 |
| 小西尚巳 | (三重県立総合病院) | ・・・ 5人 |
| 楠正人 | (三重大学消化器外科) | ・・・ 5人 |
| 斉田芳久 | (東邦大学第3外科・東邦鎌谷病院) | ・・・ 40人 |
| 田近正洋 | (愛知がんセンター中央病院内視鏡部) | ・・・ 40人 |
| 工藤進英 | (昭和大学横浜市北部病院) | ・・・ 30人 |
| 平田敬治 | (産業医科大学) | ・・・ 18人 |
| 田中信治 | (広島大学病院) | ・・・ 30人 |
| 権藤延久 | (木村病院) | ・・・ 40人 |
| 山村誠 | (神戸掖済会病院) | ・・・ 10人 |
| 飯室正樹 | (東住吉森本病院) | ・・・ 40人 |
| 李喬遠 | (守口敬任会病院) | ・・・ 10人 |
| 小澤 平太 | (北里大学医学部外科) | ・・・ 10人 |
| 鈴木貞夫 | (名古屋市立大学公衆衛生学) | |
| 城卓志・佐々木誠人 | (名古屋市立大学臨床機能内科) | ・・・ 20人 |
| 北村 信次 | (市立堺病院) | ・・・ 30人 |
| 辻井正彦 | (大阪大学医学部消化器内科) | ・・・ 10人 |
| 松田尚久 | (国立がんセンター中央病院) | ・・・ 40人 |
| 佐野寧 | (国立がんセンター東病院) | ・・・ 40人 |
| 杉本憲治 | (杉本憲治クリニック) | ・・・ 20人 |
| 高山哲治 | (札幌医科大学第4内科) | ・・・ 60人 |
| 石川秀樹 | (大阪中央病院) | ・・・200人 |
エントリー予定数の合計は814人である。全体で700人に到達した時点で終了とする。
<試験責任者・プロトコール作成補助者>
鈴木貞夫 (名古屋市立大学公衆衛生学)
<実務担当者・プロトコール作成者>
石川秀樹 (京都府立医科大学分子標的癌予防医学・大阪中央病院)
<運営委員>
若林敬二 (国立がんセンター研究所)
鈴木貞夫 (名古屋市立大学健康増進・予防医学)
石川秀樹 (京都府立医科大学分子標的癌予防医学・大阪中央病院)
酒井敏行 (京都府立医科大学分子標的癌予防医学)
松浦成昭 (大阪大学医学部保健学科)
<試験統計家>
鈴木貞夫 (名古屋市立大学 健康増進・予防医学)
<データセンター>
大谷 透 (メディカル・リサーチ・サポート)(大阪市西区京町堀2-3-1-2F)
<倫理モニタリング委員会>
| 竹下達也 | (和歌山県立医科大学公衆衛生学)・・・委員長 |
| 若林直樹 | (京都府立与謝の海病院内科) |
| 平栗勲 | (弁護士) |
| 辻直子 | (近畿大学堺病院消化器内科) |
― 16.予算 ―
厚生労働省第3次対がん総合戦略研究事業の研究費を用いる。
参加者には、各施設の責任者より、お礼として試験開始時点に5,000円、2年目内視鏡時に5,000円相当のプリペイドカードを参加者に直接お渡しし、受領書に署名を得る。
― 17.参考文献 ―
1) Gann PH, et al. Low-dose aspirin and incidence of
colorectal tumors in a randomized trial. J Natl Cancer Inst. 85: 1220-1224,
1993.
2) Baron JA, et al.
A randomized trial of aspirin to prevent colorectal adenomas. N Engl J Med. 348:
891-899, 2003.
3) Sandler RS, et al. A randomized trial of aspirin to
prevent colorectal adenomas in patients with previous colorectal cancer. N Engl
J Med. 348: 883-890, 2003.
4) Takayama T, et al. Aberrant crypt foci of the colon
as precursors of adenoma and cancer. N Engl J Med. 339: 1277-1284, 1998.
5) Antithrombotic Trialists’ Collaboration. Collaborative meta-analysis of
randomized trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial
infarction, and stroke in high risk patients. Brit J Med. 324: 71-86, 2002.
― 18.JCOG毒性基準 ―
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4) 臨床試験の方法及び期間 <服薬日誌>
(11) 健康被害の補償に関すること この試験が原因で、副作用など何らかの健康被害が生じた際、必要な治療は病院が提供しますが、治療費用の支払いはあなた様が加入している保険が支払うことになります。本試験ではお見舞い金や各種手当てなど、健康被害に対する特別な経済的な補償は準備しておりませんことをご了解ください。 (12) その他 全試験が終了後、ご希望があれば試験結果ならびにあなた様の飲まれた試験薬にアスピリンが入っていたかどうかにつきましてもお教え致します。 結果が判明し、低用量アスピリンの大腸がん予防効果が明らかになった場合、低用量アスピリンの服用を希望される方には、有償となりますが、入手できるよう対応させて頂きます。 本試験における試験薬やアンケート調査は研究費でまかなわれ、あなたへの負担はありません。それ以外の検査や診察費につきましては、現在の保険制度で適応が認められており、それらにかかる費用は医療保険制度により支払われます。 参加のお礼として、参加時点で5,000円、試験終了時に5,000円相当のプリペイドカードを差し上げます。 <必ずお守り下さい> ※ 試験期間中に新たな薬の服用を開始されるときや上部消化管内視鏡検査など出血の危険性のある検査をうける際には、以下の書類(「主治医の先生へ」)を主治医に見せて、試験薬を中止すべきかどうかを判断してもらってください。新たな薬の服用に伴い試験薬を中止するような場合は、試験は中止になりますので必ず、主治医又は事務局までご連絡下さい。 ※ 試験期間中は、バッファリンやセデス、ロキソニンなどの痛み止めや解熱剤の服用は最小限にとどめてください。もしも、服用されたときには、服用日誌にご記入ください。 ※ 新たな薬を服用されるとき、上部消化管内視鏡検査など出血の危険性のある検査・治療をうけられる際には、主治医の先生に下記の文章をお見せください。 ***************************** 主治医の先生へ この患者様は、現在、厚労省第3次対がん総合戦略事業の臨床試験に参加されています。現在、バイアスピリン(100mg/day)またはプラシーボ(偽薬)のいずれかを試験薬として服用されています。もしも、医学的にバイアスピリンやワーファリン、パナルジンなど抗血栓剤、抗凝固剤の服用が必要な場合には、試験薬の服用を中止する必要があります。今回、投与されます薬がこれらの抗血栓剤、抗凝固剤に相当するかどうかをご判断頂き、それらに相当する場合には、私どもの試験薬を中止するように患者様へご説明をお願い申し上げます。また、出血の危険性のある検査・治療が必要な場合にも、患者様へご説明のうえ、試験薬を中止するようお願いいたします。
※参加の条件は以下の通りです。
※参加の条件は以下の通りです。
― 食事と生活調査票 ―こちらをクリックしてください。(PDFファイルでご覧になれます。)― 参考資料 ―倫理モニタリング委員会手順書
このページのトップへ戻る J-CAPP Studyのトップページへ戻る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||